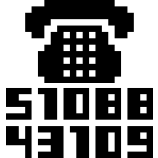なんの脈絡もなく問われ、ルエリシアはきょとんと首を傾げる。どう、とは?
すっかり戦いの傷も癒えたサクラはしばらく前に退院しており、今は13班の女部屋のソファに部屋着姿で寝そべって退屈そうに古雑誌をめくっていたところだった。
「……? 何が?」
「別に何ってわけじゃないけど。……ほら、例えばジムノとのこととか。何か進展ないの?」
進展。その単語にルエリシアはますます首をひねる。進展とは?
サクラがどういう話を聞きたがっているのかルエリシアにはさっぱり分からないが、サクラの言葉が足りないのではなく自分の知識かあるいは察する力が足りないのだ、とは薄々察している。
だからその言葉の意図を尋ねるのも野暮ったい気がするし、とはいえ勘に任せて適当な言葉を返すととんでもなく的外れになりそうな気がする。……と、そんなことを少しだけ無言のままで悩んでみると、サクラはそれを待たず訝しげな顔。
「……。……念のため訊くけど、アンタたちって付き合ってるのよね?」
「えっ?」
付き合う。この文脈における意味は理解しているつもりで、しかし自分たちの関係にわざわざそんな名前を付けた覚えはなく、上手く答えることはできなかった。
「……あ、ああー……そっか。そういうことになる……んだよね?」
「イヤ、なんでアタシに訊くのよ?」
サクラはそう突っ込みの声を上げ、それからのそのそと身を起こすと雑誌を閉じてテーブルの上へと放る。
「……なんか心配になってきた。アイツ、ちゃんとカレシらしいことしてくれてんの? 少なくともアタシがいる場だと相変わらず置物みたいなヤツだから、全然想像つかないんだけど」
彼氏。あるいは恋人。そんな表現にも強烈な違和感を覚えるが、おそらく一般的に見ればそういうラベリングで間違いはないのだろう。だからそこは飲み込むことにするが、
「……らしいこと、っていうと……?」
「ええー……例えばデートに連れてってくれるとかさあ」
サクラの疑問にも例示にもいまいちピンと来ない。例によってデートという言葉の意味は理解しているが、という話だ。
「デート……うーん。ラウンジで一緒に過ごしたりはするよ」
「……そ、そう……いや、まあそこはいっか。こんな東京じゃ行くとこなんてないし。で、二人で何してんの?」
「特別何ってことはないと思うけど……ごはん食べたり、お話ししたり……あ! ジムノくんのケガもだいぶ治ってきたから、最近はリハビリを兼ねて外を散歩できるようになってきたよ」
ここ数日の進展といえばそれだ、と声を弾ませたルエリシアだったが、サクラはなんともいえない苦い表情。
「……イヤ、うん、まあ確かにそれは喜ばしいコトだけど、そーいうんじゃなくて……えっと」
彼女には何か具体的に言いたいことがあるようにも見えるのだが、言いにくいらしい。しばしどこへともなく視線を彷徨わせ、それからソファの隅に追いやられていたクッションを掴んで抱き締めるようにして、まるで何かを決心したようにやや上目遣いでぐっとルエリシアを見据えた。
「その……。……好きだって言ってくれたり、……キ、キスしてくれたり……するの?」
「え」
少し赤い顔で真剣にそう問われ、ルエリシアはそれにやや気圧されてから記憶をたどり、
「ないかなあ」
と答える。サクラの眉が顰められる。
「……え、何? ないって、どっちの話?」
「両方」
「な……マジで⁉ ちょっと待って、まさか、今まで一度も⁉」
信じられないとばかりに声を荒げた彼女には何故か怒りにすら近い感情が透けていて、なんとなく素直に答えるのは怖いように思えたが、それでも結局ルエリシアは頷いた。ほとんど同時に盛大な溜息。
「……いやあ……なんつーか……。……アンタ、それで不満とかないワケ……?」
「不満……? ない、かなあ」
「そ、そう……そりゃアンタがいいならいいけどさ……。……わっかんないなあ……」
「……どうかしたのか?」
屋上のフェンスにもたれて、ジムノと二人並んで座っている。別に何をするでもなく、夕陽がビル群の縁の向こうに消えていくのを眺め、茜色と群青色の重なった空に星が輝きはじめるのを待つ。これだけでも充分すぎるほどに幸せだ、とルエリシアは改めて思うのだ。
彼の顔を見上げてみれば彼はすぐに気付いてくれて、こうして問いかけてくれて。視線の絡まりが熱を持っているように感じられて、肩を抱いてくれている手のひらの力と温度がじんと心地好くて。少し肌寒いのを言い訳にして身を寄せ合うのも、指先を触れ合わせたり絡めたり解いたりするだけの無言の会話も、
「大好きだよ」
ふとしたことですぐにじわりと赤く染まる頬や耳も、照れを誤魔化すようにぐいと強く抱き寄せてくれるのも。そんなすべてが愛おしくて、不満などあろうはずもない。
「……僕もだ」
けれど、好きだという言葉を貰えたら、確かにそれもまた幸せなのだろう。――欲張ってみても、いいのだろうか? そんな言葉での意思表示など蛇足だと思えるくらい、自分なんかの身には余るほど愛してくれているのはわかっているというのに。
ぎゅう、としっかり抱き締められて、それに応えて抱きつき返す。詰襟と赤い首の境界を視線でなぞりながら迷っていると、困惑と不安の微かに透ける無表情に見下ろされた。どうやらほんの些細な悩みの存在に気付かれたらしいということに驚き、それから嬉しくなり、ルエリシアはジムノの肩へと頭をしっかり押し付けて笑う。こうすると彼の低い声が直接頭に響くのが好きだ。心音を感じられるのが、深い呼吸が見えるのが、好きだ。
「……好き、って言って?」
そうねだってみると、彼はぴくりと一瞬だけ目を見開き、どこか困ったようにほんの少し眉を傾けた。何か言い淀むように言葉はないまま唇をゆるりと動かし、また閉じる。
おや、とルエリシアは内心首を傾げた。
確かに今まで彼からその単語を聞いた記憶はないのでサクラにはああ言ったが、別に、何か理由があってのことではないと思っていたのだ。ただの会話の流れ。だから、この我儘も、特別なことを頼んだつもりはなくて。
だが彼は明らかにどうすべきか迷うような気配を滲ませ、そうしているうちに言葉を発さずにいることに焦ったのか「ええと、」と上ずった声を上げ、気まずそうに
「……その……決して好きではないとか、言いたくないとかいうわけではなく……」
ともごもご呻いたのち、深呼吸でルエリシアの頭をゆっくり揺らした。
「何度も……そう、言おうとして。だが、……そんな言葉では足りないと思うと、言えずにいた」
「足りない?」
ルエリシアがそうきょとんと問い返すと、抱き締められたその腕の力がぎゅうっと強まった。
「……。……僕にとって、君は……。……僕の世界の中心で。価値観の根幹で。幸せという感情そのもので。生きる理由で」
低い声が頭を痺れさせる。全身をじわりと満たす。
「その君に対する思いは、好きだとか、愛しているだとか、そんな平凡な言葉では……足りない。伝えられない。到底、言い表せないんだ。だがどんなに考えても……未だに、適当な言葉が……見つからなくて」
今まであまり聞いた覚えのない、悔しそうな声音。ルエリシアはそれに小さく笑うと、もぞりと顔を上げた。
「ふふ。あんなに本を読むジムノくんにも見つからないなら、そんな便利な言葉はきっとどこにもないんだよ」
困ったような視線。それがなんだか無性に愛おしくて、ルエリシアは少し身体を伸ばし、彼の首にぎゅっと両腕を絡めた。頬と頬をぴたりとくっつける。熱い。
「……それに。わたしはちゃんとわかってるつもりだよ? すごく……大切に、特別に、想ってくれてること。何も言わなくたって伝わってるし……それなら、好き、っていう言葉だけだって、伝わるよ」
「……!」
微かに、息を呑むような気配。
「あ、えっと……でも。そもそも何か深い意味があってお願いしたわけじゃなくって、軽い気持ちで言っちゃっただけだから、どうしてもってわけじゃなくて――」
「ルエリシア」
真剣な声と共に、少しだけ身体を引き剥がされ、至近距離で正面から視線が絡んだ。
「好きだ」
わずかに上ずった声。
彼は真剣な顔ではっきりそう言った後、しかし結局すぐにもどかしそうな様子で、
「……それから……この先も、ずっとこうして隣にいてほしい。隣にいたい。同じ時間を共有していたい」
と、ややたどたどしくも続ける。
「笑っていてほしい。幸せでいてほしい。幸せに……したい。それから……」
必死に言葉を探す様子に、ルエリシアは思わず表情を緩めた。
「……もう。ちゃんと伝わってるってば」
それに彼は「う」と恥ずかしそうにようやく口を閉じた。
だが、ルエリシアにも彼の心情はなんとなく理解できる。要するに、自分に自信がないのだ。それは彼女も同じで、言葉を重ねていなければ、あるいはこうして物理的に繋がっていなければ、どこかちりちりとした不安を感じることがある。
「ふふっ。でも、ありがと」
深く愛してくれているのは理解している。だからこそ不安になるのだ。自分なんかに、本当にその価値があるのか? そのうち自分より相応しい誰かに取って変わられるんじゃないか? 自分の想いは本当に伝わっているのか? 繋ぎ止められるのか? そんな不安。
だから、ルエリシアはまたぎゅうっと彼に抱き着く。頬と頬をぴたりと合わせる。できるならずっとこうしていたい。彼もまた抱き締め返してくれて、頭をゆっくり撫でてくれて、それから二人で笑い合うのだ。