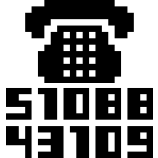否、正確に言うと、平和な世界での最後のハロウィンの日はいつにも増してうんざりとするような記憶ばかりの一日だった。
高校に入って初めてのハロウィンでもあり、渋谷の馬鹿騒ぎを見た最初で最後の日でもある。騒ぐ口実を求めて大勢が渋谷に押し掛けることは知ってはいたが、実際に目にすると閉口するばかりの騒々しさだった。渋谷エリアの外れに位置していた学校もその日は朝からずっと妙に浮ついた独特の空気に満ちていて、そんな日は決まって不快なことばかりが降りかかるのだ。
だから。
「……本当にこれを着るのか?」
ジムノは渡された衣装をつまみ上げ、極めて苦々しい声音で、往生際悪くも、そう問うた。
「しつっこいわねー。そのいつもと変わんないよーな地味な服にどんだけ文句言うつもりなのよ。さっさと着替えてきなさいっ」
猫の耳のようなものを着けて珍妙な服に身を包んだサクラが口を尖らせる。
――あれから一年、滅びかけた世界での最初のハロウィン。
これから本格的に復興の道を歩もうというところで、SKYか誰かの発案で、都庁全体を巻き込んだハロウィンイベントをやろうという話になったのだ。
とはいえ大掛かりなことが出来るわけでもない。都庁各所にそれらしい飾り付けを多少施して、ムラクモと自衛隊とSKYから募った有志で賞味期限の切れそうな戦前製の菓子を配り歩いて、エントランスにも菓子を設置しほんのささやかなパーティーをしようというだけだ。
有志と言いつつも13班は強制参加に等しく、それを真っ先に察したエリシャは敢えて自ら手を挙げ衣装係を引き受けることで当日の面倒ごとからは逃れることに成功している。彼からぞんざいに渡された衣装は吸血鬼をイメージしたものらしく、タイの付いたシャツとスラックスに黒いマントを羽織るだけという、嫌がるジムノに対する配慮も感じられなくもないような、比較的無難なものではあった。それでも嫌なものは嫌なのだ。
ジムノは仕方なく衣装を抱えた代わりに溜息を吐き出し、着替えるために自室に戻ろうと重い腰をようやく上げたところで、ちょうど扉が開きルエリシアがおずおずと顔を出した。
「着てみたけど……どうかな? おかしくない?」
彼女の艶やかなブロンドが映える、黒を基調としたふわりとしたマットな質感のワンピース。つばの広い三角帽子や羽織ったマントも黒に統一されており、その代わりに紫色と橙色のリボンやタイツが程よいアクセントとしてあしらわれている。
彼女はジムノを見上げて少しだけ恥ずかしそうにはにかんだ。
それに彼は心臓を鷲掴みにされたように感じ咄嗟に声が出ず、可愛い、と口にするよりも早く、
「あら、バッチリじゃない!」
とサクラが明るく応えてしまった。
「ほんと? 良かった。ちょっと恥ずかしいけど、雰囲気はあるよね」
「さすがエリシャのセレクトよね。こーいうのはよく分かってんじゃない。……ほら、ジムノもさっさと着替えてきてってば」
ついじっとルエリシアを見つめてしまっていたジムノは、そう急かされもう一度溜息を吐く。
「……嫌がってるのを無理にやってもらわなくていいと思うけどなあ……」
「何言ってんのよ、こーいうのもアタシたちの仕事なんでしょ。それに、アンタだって楽しみにしてたじゃない」
苦笑するルエリシアに、サクラは大量の菓子を手持ちサイズの籠に詰めながら口を尖らせる。
「……そうなのか?」
目立つことを好まないルエリシアがこういったイベントを楽しみにしていたというのは少し意外で――そういう解釈だとするとサクラの言葉はやや意味が通らない気がしつつも、ジムノはルエリシアにそう問う。
彼女はやや困ったような笑顔を浮かべてごまかそうとしているようだったが、
「……ジムノと一緒にハロウィンパーティーなんて夢みたい、って目をキラッキラさせてたじゃないの」
と半眼のサクラに憮然と言われ、「う」と小さく呻いた。
「そっ、それはそうだけど……別に服くらいはいつもどおりでも……」
「すぐ着替えてくる」
「わーっ! ご、ごめんねっ!?」
ルエリシアもまた彼がこういうものを好まないのを理解していて、それ故に面と向かって言うのは憚られたのだろう。
慌てるルエリシアに小声で「後で一緒に過ごそう」と伝えると、少しばつの悪そうな表情を浮かべていた彼女は、結局にへらと笑った。
「……うん! ありがとう」
やはり騒がしく浮ついた空気は好きになれない。
だが、それはそれとして、楽しそうな様子で菓子を配り歩く愛らしい格好のルエリシアを見ているのは当然好きだし、彼女が一緒に過ごすのを楽しみにしてくれていたのだと聞くと浮ついた気分にもなるし、そのためなら仮装して荷物持ちをすることだってどうということはなかった。
「また空になっちゃった。みんな楽しんでくれて良かったなあ」
ルエリシアはジムノの持つ大きな紙袋から手持ちの籠へと菓子を補充しつつ、上機嫌に笑う。
行く先々でルエリシアとサクラの周りには人だかりができていて、誰も彼もが楽しそうにしている。ドラゴンの脅威こそ去ったものの厳しい生活の続く都庁の雰囲気を和らげたいという目的もあったこのイベントだが、むしろ我先にと13班への労いの言葉をかけてくれていた。
「……そうだな」
世界を救うという崇高な目的で戦ったわけではない。だが結果として勝ち取れたものの一部を実感できたようで、悪くはないと思えたのだった。
十月の末にもなると、夜は随分と冷える。
「みーつけたっ」
屋上のフェンスに身体を預けて闇に包まれた東京をぼんやりと眺めていたジムノは、弾む声に首だけで振り向いた。
「もう終わったのか?」
ぱたぱたと駆け寄ってきたルエリシアはそのままの勢いで彼に飛び付いて、楽しそうな様子でぎゅうっとしがみつく。彼と同じく仮装のまま、ただ帽子だけどこかに置いてきたようだった。
「ううん、こっそり抜け出してきちゃった」
菓子を配り歩いた後は、彼女が楽しみにしていた通りにエントランスでのパーティーに参加した。会場の片隅で皆の楽しそうな様子を二人でゆっくり眺めているつもりだったのだが、あっという間にルエリシアは人の輪に代わる代わる引っ張られて行ってしまい、手持ち無沙汰になったジムノは仕方なくこの屋上で暇を持て余していたのだった。騒がしい空間に一人でいるのは好きではない。
「君を独り占めしていたら怒られそうだな」
「でもわたしはジムノくんといたいんだもん。……ああいうのも13班のリーダーの務め、っていうのは分かってるけどさ。それに……」
ルエリシアは少し寒そうに彼のマントの内側に潜り込んでくる。彼は片手で彼女の肩を抱き寄せてもう片手でマントが風にめくれないよう押さえてやった。
「……なんだかもやもやしちゃって。真竜に勝てたのもジムノくんやエリシャのおかげなのに、一緒に歩いててもわたしばっかりお礼を言われて、褒められてさ……」
彼女は口を尖らせた。
ひんやりとした空気と、満月のふわりとした光とが心地よく満ちる空間。こうして二人並んで外を眺めるのももはや何度目だか分からないが、初めて二人で迎える季節の訪れを意識すると、自然と頬が緩んだ。
「君が13班の顔だ。それに、僕も……たぶんエリシャも、仮にああやって囲まれても困るだけだしな。僕たちの分も君が受けてくれるのは助かる」
「ええー……わたしだって、ああいうのは得意じゃないんだけどなあ……」
「はは」
小さく笑って、細い肩を撫でる。それに彼女も顔を綻ばせ、猫のように身を擦り寄せてきた。暖かい。
しばらくはそのまま互いの体温を混ぜ合わせるように身を寄せ合っていたが、ふと、彼女が「あ、そうだ」と何か思い出したように顔を上げた。月明かりに煌めく碧眼にじっと見上げられ、どきりと心臓が跳ねる。
「トリック・オア・トリート」
期待の籠った声。ジムノは慌ててポケットを探るが、何も持ってはいない。
「……後でもいいか?」
「だめ。じゃあ、イタズラね?」
にまりと笑うルエリシアに、一体どんな悪戯をしてくれるんだ、と口走りそうになるのを飲み込む。
「ちょっと、耳貸して?」
「? ああ」
彼女の高さまで身を沈めると、彼女の腕がするりと首に巻き付き、耳に触れそうなほど近くまで唇が寄せられる。夜風に混じる吐息を確かに感じて身体の芯がぞくぞくと震えた。
愛の言葉でも囁いてくれるのだろうかと馬鹿な期待をしてしまいながら、聴力に意識を集中させていると――
かぷ、と耳たぶを噛まれた。
「っ……!?」
全く予想外の悪戯に妙な声を上げかけたのをなんとか飲み込み、だがそれ以外のリアクションを取ることもできずに固まってしまった。そんな彼の様子を面白がっているのか、ルエリシアはそのまま何度も甘噛みを続ける。
唇と歯の感触にばくばくと心臓が喧しく、たまに舌が触れると破裂しそうにすら思えて、
「……ルエリシア」
と名を呼ぶだけのほんの微かな抵抗をする。彼女はその意図を理解してか、唇を数ミリ離してくすくすと小さく笑った。それはそれで心臓に悪い。それからもう一度だけかぷりと噛んでから、ようやく満足したのか顔を離す。
「ふふっ」
ルエリシアは全く照れもせずただただ楽しそうで、そんな様子にジムノはなんとなく負けたような気がしてしまう。
……今なら同じ悪戯をしても許されるだろうか?
いや、彼女ならいつ何をしてもきっと許してくれるのは知っている。自分が許すかどうかだ。
だから、
「……トリック・オア・トリート」
視線すら合わせられないままに彼女に判断を委ねてみると、彼女はまた小さく笑い、それからワンピースのポケットから飴玉をひとつ取り出した。
「はい、どうぞ?」
くるりと包み紙を開き、月明かりをきらりと反射する宝石のようなその飴玉をつまみ上げると彼の唇へとねじ込む。その細い指先に甘く噛みついてやろうかと一瞬だけ迷ったが、結局そんな勇気は出ず、飴玉だけを受け取ったのだった。