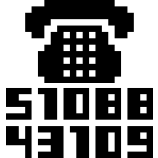ジムノがふと目を覚ますとどうやら既に夜になっているらしく、暗闇に薄い光が浮かび上がっていた。
ごそごそと小さな物音に気付き、彼はそちらに視線を向ける。
そこではルエリシアが彼に背を向けていて、白い背中に垂れたブロンドがさらりと揺れていた。
その光景をぼんやりと眺めながら、白い服なんて持ってきていたかとしばらく記憶を辿り、それからようやく、その背の白さは服のせいではなく素肌であることに気付いた。
心臓が跳ね上がる。
彼は危うく声を上げかけたのをなんとか抑え、これは一体どうするべき状況であるのか、眠気の残る頭で考えた。
何も見なかったことにして二度寝を決め込むべきなのか。
いくら寝ているといっても人前で着替えるなとでも言うべきなのか。
しかし。
「……?」
固まったまま――つまりじっくり彼女の背を凝視していると、あることに気が付いた。
その肌がところどころ変色していたり、妙な線が入っていたりする……ように見えるのだ。
それはその小さな背の全体に見られ、彼は内心首を傾げる。
薄暗い上に、長い髪に隠れて見えづらいが――さらに目を凝らすと、それは傷跡のようにも見えた。
――背中の、傷。
彼には原因が一つしか思い当たらず、背筋が冷えるような感覚に思わず飛び起きた。
「ルエリシア!? その傷っ……」
「きゃあっ!?」
しまった、と思った時には当然手遅れだった。
彼女は悲鳴を上げ、慌てて手近なブランケットを上半身に巻き付けながら彼の方を恐る恐る振り向く。
「あっ……! い、いや、すまない。今目が覚めたばかりで、決して着替えを覗き見るようなつもりはっ……」
こんな馬鹿な言い訳をする羽目になったのは初めてだ。彼はしどろもどろに視線を外す。
「だ、大丈夫……。その……寝てると思ってたから……びっくりしただけ……」
そう言いながらも、彼女はブランケットに自分の身体を包んだまま、少し強張った表情を浮かべる。
いや、今はそれよりも。
「……。……その傷」
彼がもう一度顔を上げてそう口にすると、ルエリシアはびくりと身を竦め、何かを怖がるように視線を落とした。
「僕を庇った時に……」
「……えっ、あ、違う違う!」
彼女ははっとして顔を上げるとぶんぶんと首を振り、慌てて否定した。
「……違うよ。これは……昔の傷だから……大丈夫。昼間の怪我はちゃんと治ってる」
「昔の……?」
背中全体に走るいくつもの傷跡。一体何があればそんなことになるというのか。
「……今はもう、体には障らないのか?」
そう問うと、ルエリシアはきょとんとして、それから、今度は何故か少し嬉しそうに笑った。
「もちろん。なんともないよ」
「そうか。……良かった」
何の傷かも分からないのに、良かった、という言葉は軽率だったような気もしたが、彼女はすっかり肩の力を抜いていて、
「ありがとう、心配してくれて」
と、また笑う。
その表情にまた胸が苦しくなり、しかし思わず見とれてしまう。それから、ようやく彼女が極めて無防備な状態であることを思い出し、慌てて背を向けた。
「ああ……ええと……悪かった」
「え?」
何故謝るのか、と言わんばかりの反応。
「いや……その……。……服を、着てくれると……助かる、というか……」
「あ、そっか」
彼女はけろっとした様子で答える。
衣擦れの音がなんとなく気恥ずかしい。おそらく顔が赤くなっているような気がする。薄暗くて良かった、と彼は安堵の息を吐いた。
「……背中だけじゃ、ないんだ」
それからは、ただ朝を待っていた。
二人で並んで座り、黙ってぼんやりとして。ジムノも、そしておそらくルエリシアも眠る気にはなれなかった。眠っておくべきだとは分かっていても。
そんな中、唐突に呟かれた言葉の意味を咄嗟に飲み込めなかったジムノは、え、と短く問い返す。
彼女に視線を移すと、長い髪にこびりついてしまっていた血や汚れを地道に取り除き続けていた。
肌や髪が気になってなかなか着替えられなかったために深夜に彼女の無防備な姿を目にしてしまう羽目になったようで、お風呂に入れればすぐなのにな、と一度だけ口を尖らせていた。
「傷跡。顔と手先以外、全身にたくさんあるの」
どうしてわざわざそんなことを話すのだろう、と思うと、どう答えればいいか分からなかった。
長い髪に視線を落としたまま薄く笑っている彼女はまるで自分で自分の傷を抉っているように見えて、直視できない。
苦しい。
「ほら、こんな感じ」
彼女は作業を止めると片方の袖口を少し捲り、笑顔で見上げてきた。
手首よりも上、ほんの十数センチの範囲にいくつかの傷跡が浮かんでいる。
闇に溶けていきそうな黒いブラウスの下にも、長いスカートの中にしまい込まれた脚にも、同じような傷が残っているのだろう。
だがその傷跡よりも、無理矢理笑ったような表情が、苦しい。痛い。
違う。見たいのはそんな苦しそうな笑顔じゃない。
「……ジムノくん?」
視線が腕ではなく顔に注がれていることに対してか、ルエリシアは少し訝しげに首を傾げた。
無言のまま、捲られた袖を元に戻してやる。その拍子に微かに触れた指先の温度は彼よりも少し低くて、その手を握りしめたくなった。
「……無理をするな」
「してないよ」
「してる!」
彼女が努めて明るく答えようとしているのがはっきりと分かり、思わず少し声を荒げた。
いや、分かってはいないのかもしれない。ただ、彼自身が酷く苦しいことだけは確かだった。
彼女の幸せそうな様子を見ているときの、心臓の奥が熱くなるような苦しさとは違う。まるで溺れるような、あるいは胃のあたりを刺されたような苦しさと痛み。
それはきっと彼女が苦しいからだと思うのだ。
――随分と不便な感情だ、と彼はまるで他人事のように思う。彼女が苦しんでいると自分まで苦しく感じるなんて。
ルエリシアは驚いたように目を見開いていくつか瞬きをして、それから、今度こそ、少し安心したように笑った。何故そんな反応をするのかも分からないまま、その表情だけであっさりと苦しさが和らぐのを彼は自覚する。
こんなにも簡単に自分の感情が振り回されることなんて今までなかった。
本当にルエリシアのことを好きになってしまったんだな、と改めて意識する。
「……いや。すまない。だが……そんな話、無理にしなくていいんだ」
全身に残る、尋常ではない数の傷跡。彼には想像の及ばない何かがあったのだろうが、どう考えても愉快な話にだけはならないだろう。
過去の苦しみを自分の口から話すのがそんな気軽なことではないことくらい、彼にも分かる。
「聞いて欲しいことがあるなら、聞く。だが、話したくないことまで話す必要はない」
彼はそうしてきた。
とはいえ、誰かに話を聞いて欲しいと思ったことがなく、つまりは誰にも何も話さないということだが。
「だから……その」
それ以上何と言えばいいだろう。どうすれば彼女の気持ちを楽にすることができるのだろう。どうすれば。
気の利いたことひとつ言えない自分の不器用さが憎い。
しかし、唇を噛んで考え込むジムノの顔を見上げ、ルエリシアは嬉しそうに微笑む。
「……ありがとう」
「……え」
「やっぱり、ジムノくんと出会えてよかった」
その言葉にどきりとする。馬鹿みたいに嬉しい気分になって、体温が少し上がったような気がする。
彼がその言葉の意図を問う前に、
「じゃあ、これは聞いてほしいことなんだけどさ」
と切り出して彼女は苦笑した。
「家を出てから……この一年間で。何回か知らない人に手とか足とか……傷を見られちゃうことがあったんだけど。みんな、まずは『うわっ』て顔をして、それから見ないフリをしながらちらちら見て、で、人によっては『それ何の傷?』って興味本位で尋ねてくるんだよね。サイキックも傷跡も気味悪がられるし……そもそも、見た目が日本人じゃないっていうだけで、みんなの視線が違う」
そうだろうな、とジムノは心の内だけで答える。
多くの日本人は『普通』に拘るものだ。
東京には外国人が溢れているとはいえ、それでも電車で隣に立った時に、コンビニの店員だった時に、道端で話しかけられたときに、その人間が外国人であるという事実に多少なりとも意識が向く人間が多数派ではないだろうか。それに差別意識を持つか、助けが必要かどうかというボランティア精神――場合によってはそれに似た傲慢な優越感を持つか、恐れや警戒心を持つか、それとも何とも思わないかは別として。
別に外国人かどうかだけではない。彼にも心当たりがいくつもあった。
彼女とは違い、外見が極めて地味で平均的なのは自他ともに認めるところであったが――例えば左利きだというだけのちょっとしたマイノリティでも充分に特異な扱いをされた覚えがあるし、望まずして人並み外れた剣道の腕や、好きで真面目に取り組んでいる学業の成績でも、不快な思いをすることは数えきれない程にあった。……彼の場合は多少自業自得であることを、自覚はしているが。
成績ごときでそうだったのだから、まして多くの人に忌避されるであろうサイキックや傷跡のために受けた苦しみは察するに余りある。
「東京なら人もたくさんいて、居場所もあるかなあ、なんて思ってたんだけど。そんなこと……なかった」
彼女は寂しそうにそう呟いた。
居場所。
「だから……だからね、ジムノくんに出会えてよかった、ってすごく思うんだ。助けてくれて、サイキックのことも傷跡のことも気持ち悪がらないでいてくれて、一緒にいてくれる人で……本当によかった」
ぎゅう、と胸が苦しくなる。彼女の過去の辛さと、そんな風に言ってくれる幸せとが混じり合って、やっぱり、苦しい。
「……水道、止まっちゃったみたい」
困り顔のルエリシアはトイレの扉を閉め、肩を落とした。
夜が明け、二度目の朝を迎えて。
出掛ける準備をしながら――といっても荷物があるわけではなく、表を通り掛かった化け物や人間に見つからないよう室内を片付けておくだけだが――ジムノもまた唸る。
「……そうか。さて、どうしたものか……」
最初に想定していたよりも随分早い。
恐らくは、至る所から樹木が生え出した影響で、地下の水道管が破損してしまったのだろう。しばらくは残っていた水が出ていたのだろうが、これ以上はどうしようもなさそうだ。
元より飲んだり触れたりするのは避けてペットボトルの水を使っていたが、それを水道代わりにトイレに流すにはさすがに勿体ない。それ以前に、下水道も破損している可能性を考えると、ここはこれ以上使うべきではないだろう。
「ひとまず今日明日は携帯トイレと……後は、他の建物を探してみてもいいかもしれない」
彼はそう言ってはみるが、いずれも一時しのぎでしかない。仮に破損していない水道管が通った場所を運良く見つけられたとしても、ずっと使い続けられるわけでもないだろう。
「そうだね……。じゃあ、そろそろお出かけする?」
「ああ」
結局昨日はあまり行動範囲を広げられなかった。今日は状況の把握や物資の調達を進めたいところだ。
「体調は本当に大丈夫なんだろうな?」
「もうなんともないってば。朝ごはんもたくさん食べたし、元気だよ」
ルエリシアはにっこりと笑った。ほんの少しだけ大きい服が心許ないようで、時折首元を隠すように襟ぐりを握りしめている。
「それならいいんだが。……新しい服も探してこよう」
ボタンで締まる袖とパンツスタイルは安心感があると満足げだったので、次に自分が服を選ぶことになったときはできるだけ全身を隠しやすいものにしよう、と考える。
彼女は自分の動作を初めて自覚したようにはっとした。
「あー……あはは。ありがとう。ごめんね、気を遣わせちゃって」
……気を遣っている?
そんなつもりはなかった。よくよく考えると自分でも驚くほど、自然と考えて口にしてしまっていたのだ。
「いや」
ジムノは短く答え、外の様子を確認してからガラスの扉を開ける。
ふわりと吹き込む空気は昨日と変わらず木々の匂いを重く含んでいて、少し暑い気がした。
一昨日は突然大量の化け物が現れ、昨日は化け物が減り人間も消えた代わりに街が森と化して。今日も何が起こっていてもおかしくないと思ったが、一見する限りは昨日と変わりないようだった。化け物の姿もなく、それでも少し警戒しながら、今日もまた道玄坂を渋谷駅方面へと下ってゆく。
「いい天気だね」
「そうだな」
ジムノは話を広げられないことに自己嫌悪するが、ルエリシアはそれを全く気にしていない様子で、軽い足取りで坂を下る。
そうしているうちに、道玄坂上の交差点に差し掛かった。表通りを歩くべきか、マークシティの中を通ってみるべきかと少し迷う。かつてはここからマークシティを通れば雨に濡れることもなく渋谷駅を出るすべての電車に乗ることができる、いわば『安全』なルートだった。
しかし今は――ここに限った話ではないが、建物に入ることはリスクが高いように思える。食料や日用品などの物資を確保するためには入らざるを得ないのだが、地下から樹木が生え出してきた影響で建物が崩落する危険もあれば、化け物が住み着いている可能性もある。協力的な人間がいるかもしれないが、そうでない人間がいるかもしれない。現状の把握という意味では確認すべきなのだろうか?
「……あ」
ジムノがそんなことを考えていると、ルエリシアは小さく緊張した声を上げた。
「血の跡が……ある」
そしてそのままふらふらとマークシティの暗い入口へと誘われるように歩いてゆく。
「お、おい」
声を掛けても立ち止まらず、彼は慌ててその後を追った。
確かに彼女の視線の先には垂れ落ちたような血痕があり、点々と建物の中へと続いている。
「……やめておけ」
彼女の腕を掴んで無理矢理立ち止まらせた。
「でも、ケガしてる人がいるのかもしれない。放ってはおけないよ」
そう言うような気はしていた、とジムノは嘆息する。
彼女は不安げな表情で、建物の奥へと視線を向けたまま。
「……わかった。じゃあ、僕が先に行く」
「あ……。ごめんね。ありがとう」
血は既に乾きかけているように見える。もし人間が化け物に襲われたのならもう手遅れかもしれない。人間の血ではないとすれば、手負いの化け物が待ち構えているかもしれない。
「いや、いいんだ」
だが彼女が誰かを助けたいと思う気持ちを尊重したいと思った。
自分ひとりなら絶対にしない選択をしたいと思った。
血痕を追い、慎重に建物の中へと足を踏み入れる。
薄暗いが視界は問題ない。物音はしない。思いの外、危険は少ないのだろうか。化け物の気配もなく、静まり返った通路に二人分の足音だけが響いてゆく。
だが。
「……」
続く血の跡は、少しずつ大きく、多くなっている。血でできた靴跡も付き始めた。
ルエリシアはそれに気付いているのかいないのか、黙ってぴったりと後ろにくっついてきている。
所々には勢いよく飛び散ったような跡も残っており、胃の底で不快感が掻き混ぜられてゆく。
血痕は井の頭線の改札前で曲がり、その先へと吸い込まれていた。
「あ、ここって……この間の」
ほんの小さな声で、ルエリシアが呟く。
言われるまで意識していなかったが、確かにそうだ。
ルエリシアに初めて出会った場所。
自分が毎日使っていた改札。
血痕の続く先は、死角になって見えない。だが、酷く嫌な予感がして、彼は足を止めた。
「……どうしたの?」
「いや……」
彼女を背の後ろに隠し、曖昧に答えながら、よく観察する。
見慣れた景色のはずだというのに、全くそのように感じることができない。
明かりが点いていないせいか。
人混みがないせいか。
どんよりと濁った空気のせいか。
薄暗い中で彼は更に目を凝らし――ようやく、違和感と嫌な予感の正体に気が付いた。
改札機に、床に、壁に。至る所に、細かい血しぶきが付着しているのだ。
「……っ……」
思わず息を呑む。
「ねえ、どうしたの……?」
不安そうなルエリシアの声。
それにジムノはかぶりを振った。
「……駄目だ。引き返そう」
ルエリシアはその言葉の意図を理解したらしく、しかしそれでも、沈痛な面持ちで壁に隠れた改札の先へと視線を投げる。
「そこに……誰か、いたの?」
「手遅れだ」
そう答えるが、それでも彼女はジムノを追い越して歩き出した。そして、改札の前で言葉を失い立ち尽くす。
覚悟を決めて彼女の隣に並ぶと――その向こうは血の海だった。
床は真っ赤に染まり、壁にも赤い飛沫が勢いよくぶち撒けられている。
そこには誰もいなかったが、血の飛び散り方を見る限りは、突き当たりの曲がり角のさらに先にその原因があるはずだ。
ルエリシアは少し青い顔で、誘われるようにふらふらと足を踏み出す。
「おい。もう……これ以上は……」
彼の呼び掛けにも答えず、こつ、こつ、とゆっくり靴音を鳴らして開いたままの改札を抜け、乾きかけた血の上を進む。
その血の主が何であれ、どう考えてもその先には決して見たくはない光景が広がっているのだろうが――生きた化け物もいるかもしれないと思うと彼女ひとりで行かせるわけにもいかない。
数歩で彼女に追い付くと、彼女は曲がり角の手前で一度立ち止まって彼の方を振り向いた。
「……ごめんね」
ルエリシアは小さく呟く。
「分かってる……分かってるけど、わたしは……」
こうしなきゃいけないの、と言い切って、また足を踏み出し――曲がり角の奥の血溜まりの主を、見た。
「……っ……!?」
それに続いたジムノもまたそれを直視して、咄嗟に口元を押さえる。
そこに転がっていたのは大量の肉片だった。
原型を留めていないが、頭部だけは丸い形のままで二つ転がっており、少なくとも二人以上の人間がここで殺されたのだということだけはわかる。
叫び出しそうになっているのに、声が出ない。
一刻も早くここを離れたい。
ルエリシアの手を掴んでから彼女に視線を移すと、彼女は目を見開いて、散らばった肉片をただじっと見つめていた。
それにジムノはぎょっとして、咄嗟にその手を無理矢理引く。
これ以上この光景を見たくなかったし、彼女にも見せたくなかった。
彼女は抵抗するわけでもなく、ずんずんと歩くジムノに引かれるままについて来る。
そうしてまた改札を抜けて、彼はその先にあるベンチに座り込んだ。がくがくと膝が震え、しばらく立ち上がれそうにない。
「……大丈夫……?」
ルエリシアも隣にそっと座り、そう心配そうに寄り添ってくれた。
彼はそれに答えようとするがうまく言葉を出せず、顔だけを彼女に向ける。
そんな彼を覗き込んでくるその表情もまた心配そうに歪めてはいるものの、彼ほどショックを受けたというようには見えない。
「っ……。顔、真っ青だよ。しばらく休んでから移動しようか」
小さな手で背中を撫でてくれる。
まるで子供扱いでそれに少し情けなく思うが、それよりも彼女の様子の方が気になった。
「……君は……平気、なのか?」
なんとか声を絞り出す。
「……助けられなかったのは……残念だけど」
ルエリシアは弱く苦笑してそう答えた。
どうしてあの光景を見てそんな感想なのか。
それが優しさなのか、強さなのか、それとも逆に何かが欠落しているのか、彼には分からない。
そういうことではなく、と言いたくなったが、上手く声が出なかった。
代わりに、胸を押さえて治まらない吐き気をこらえながら無理矢理立ち上がる。
「えっ……ま、まだ休んでた方が……」
膝の震えが止まらないが、そんなことは言っていられない。
「……。もし……」
改札の奥に広がる血の海から目を逸らしながら、声を絞り出す。
「何かが……違っていれば。あそこに転がっていたのは……僕たちだったかもしれない」
自分でそう口にして、ますます吐き気がこみ上げる。
ようやくルエリシアは顔をさっと青くした。
自分のことはまだ構わない。もし彼女があんな風に――と思うと、気がおかしくなりそうだった。
「……何が……あったのかは、分からないが。ここはまだ……危険な可能性も……ある」
「うん……そう、だね。……出ようか」
「……落ち着いた?」
元来た道を引き返し、外に出て腰掛けられそうな段差を見つけるなりまた座り込んで。
建物の中で吸った空気を全部入れ替えるかのように、ジムノは何度も深呼吸していた。かつての淀んだ都会の空気ではなく、森の中のような匂いが充満しているのが救いだ。
「ああ……多少は。……君は平気なのか? その……血とか、ああいう……」
もう一度同じ問いをして、あの光景について言及しようとし、しかし気持ち悪くなってきたので途中でやめる。
「……うーん、どう……かな……」
ルエリシアは曖昧に呟き、自分の手元に視線を落とした。
服の下に傷の隠れた腕を少しさすり、小さく笑う。
「慣れちゃった……のかも」
「慣れた、って――」
どういうことかと問おうとしたジムノの耳に、小さな物音が届いた。
咄嗟に顔を跳ね上げると、少し離れた物陰からちょうど誰かがこちらを伺うように顔を覗かせたところだった。
「あっ……」
ルエリシアもそちらを見て小さく声を上げる。
彼女以外に生きた人間を見たのは随分久しぶりのように感じる。
「うわ、なーんだ」
しかしその誰かはあからさまに落胆した声を上げてから姿を現した。
覚えのない顔だったが、ジムノの通う高校の制服を着た女子生徒だった。
続いて同じ制服の女子がもう一人現れ、薄ら笑いを浮かべる。
二人とも、タイの色からすると彼の同級生らしかった。
「せっかく人がいると思ったのに、よりによってムラサメじゃん。がっかり」
がっかりなのはこっちだ、と内心ジムノは毒づく。
こんな最悪な気分の時に、彼を知る人間になど現れて欲しくなかった。
彼女たちは擦り傷や服の汚れなどが見られるものの至って元気そうで、随分幸運に恵まれたようだ。
「……知り合い?」
「いいや。無視しておけ」
首を傾げるルエリシアにきっぱりとそう返す。
それに女子生徒たちは不快な声で笑い合った。
「気を付けなよー、外人さん。そんなヤツといると危ないよ」
「そーそー。怪物たちに出くわしたときに盾にされちゃうかも」
「あはは、確かに」
不快だがある意味で懐かしさすら覚える会話を特に気に留めず聞き流していると、隣でルエリシアがすっと立ち上がった。
その横顔は初めて見る表情で――どうやら怒っているらしかった。
いや、表情だけではなく、もはや殺気と言っていいほどの気配を放っている。
「おい……?」
思わず声を掛けるが彼女は女子生徒たちをまっすぐ睨んだまま、ぐっと唇を噛んでいた。
「な、なによ。親切で言ってあげてるんじゃない」
「そうだよ。そんな何考えてるか分かんないよーなヤツ、信用しない方がいいよって言ってあげてんの」
二人もその殺気に圧されたのかややたじろぎながらも、口々に言い返す。
「……何も知らないくせに、そんなこと言わないで」
ルエリシアはまるで質量を持っているかのような声で、そう言い放つ。
「おい、無視しておけって……」
「だって!」
きつく握りしめられた拳。その袖口を軽く引いて声を掛けると、彼女は感情的に声を荒げた。
「何考えてるか分からないんじゃない、分かろうとしないだけだよ! そんな人たちに、そんなこと言われてっ……!」
「……いいから」
「よくない!」
彼女は怒鳴ってから、改めて女子生徒たちに何か言おうとしたのか向き直り――
「って……う、後ろ!」
言おうとした言葉を飲み込み、そう叫んだ。
「えっ……うわっ!?」
「またウサギじゃん! ああ、もうっ!」
彼女たちは比較的運動能力が高いのか、背後から現れた兎の化け物の振るう爪を咄嗟に避けた。
ジムノは思わずふらつく足で立ち上がったが、ルエリシアの行動の方が速かった。
「もう一匹いる! 伏せて! 早く!」
鋭い叫びに二人はやや戸惑いつつも言われた通りに伏せる。
それからルエリシアの放った炎が、獲物に避けられバランスを崩した兎とその背後からさらに飛び掛かってきていた蛙を一度に飲み込んだ。
炎はあっさりと二匹を焼き尽くし、その残骸がばらばらと落下し、灰が舞ってゆく。
「あっつ……。……な、何なのよ、今の……」
「意味わかんない……アンタがやったの……?」
「……」
ルエリシアは答えない。力を少し消耗したのか、肩を小さく上下させている。
女子生徒たちは服の埃を払いながら立ち上がると、そんなルエリシアに冷たい視線を向けた。
「何よ、今の力っ……。まさか、渋谷をこんなめちゃくちゃにしたの、アンタじゃないでしょうね!?」
ジムノは思わず二人を睨みつけた。頭に血が上るのを自覚する。
だが彼女たちはそれに気付きもせず、更にルエリシアへと言葉を投げつけていく。
「何か言いなさいよ!」
「みんなをどこにやったの!?」
勝手な妄想でそう怒鳴る二人に、ルエリシアは黙ったまま、怒るでも悲しむでもなく、どこか困ったような顔。
ついに一人がルエリシアの胸倉を掴み上げようとして、しかし手を引っ込めた。
「うわっ、ホント何なのよ、コイツ。傷だらけじゃん。気味悪い」
「――おい」
ジムノはとうとう我慢できずに声を上げる。自分でも驚くほど低い声が出た。
慌てて襟ぐりをぎゅっと握りしめたルエリシアがはっとして振り向いてくるが、そんな彼女の手を引いて背後に隠すようにし、女子生徒たちを正面から睨む。
正直なところ殴り飛ばしてやりたいと思ったが、今はそんな体調でもない。化け物が現れたときもほとんど反応できなかったのだ。
胃がむかむかする。その原因がすり替わったような気もするが。
「黙れ。助けてもらっておいて礼を言う気もないならさっさと消えろ」
代わりにそう言い放つと、彼女たちは少しだけ驚いたようだった。それもそうだろう。反応すればするほど何倍にもなって返ってくることを学んでからは、ただ無視するだけだったのだから。こうして怒りを露にして言い返したことなどいつぶりだろうか。
しかし結局、二人は怒りや不信の入り混じったままの表情を隠しもせず、何やら捨て台詞を吐きつつもようやく踵を返して去っていった。
「……今日も朝から散々だな」
彼は盛大に溜息を吐く。
堪え難い光景を見る羽目になり、ようやく人間に会えたと思ったら彼を嫌う同級生で。
「すまなかった」
そいつらに、ルエリシアまで傷つけられてしまって。
彼女は少し疲れたのか、元のところに座り直し、首を傾げた。彼もその隣に腰を下ろす。
「?……どうしてジムノくんが謝るの?」
そう問われると少し困る。
彼女たちが余計なことを言う前に追い払えば良かった、とか。
それ以前に、最初に自分が何か言い返すべきだった、とか。
そもそも今までまともな人間関係を作ってこられなかったせいだ、とか。
「もっと……上手くやれたはずだった」
それだけ答える。
そう、やれるはずなのにやらなかったことが、今までいくつもあった。
他人に嫌われても構わないからと開き直って逃げて。
そのツケがついに今日、ひとつ回ってきたのだな、と感じたのだ。
よりによって、自分ではなく、好きになってしまった人を傷つけられるという形で。
しかしその彼女は笑ってかぶりを振った。
「ううん、大丈夫だよ。わたしこそ……ごめんね。無視しろって言われたのに、つい……カッとなっちゃって」
「いや。その……。……代わりに怒ってくれるとは……思っていなかった」
今まで、何を言われようとも、その場で真っ向から反発してくれる味方などいなかったのだから。
嬉しかった、と言おうとして、なんとなく気恥ずかしくて口ごもる。
「……だって……悔しかった。ジムノくんは、一昨日からずっと……わたしのこと、何度も助けてくれてるのに。なのにあんな風に言われて……すごく悔しかったの」
真剣な顔でそう言ってくれる彼女に、ジムノは「ありがとう」と答える。
「だが……まあ、本当のことだ。君じゃなく彼女らだったら本当に盾にでもするかもしれないしな」
少なくとも彼女たちを助けるようなことは、自分ならしなかっただろうと思う。それだけの価値を感じないからだ。
しかしルエリシアは誰かが助けを待っているかもしれないからと危険かもしれないところに足を踏み入れ、忌み嫌われることを自覚している力を晒してでも一瞬前まで怒鳴りつけていた見知らぬ相手を助けるような人間なのだ。そんな彼女に代わりに怒ってもらうような価値は自分にはない、と思ってしまう。
しかしジムノの台詞を非難するわけでもなく、彼女は小さく笑った。
「ジムノくんも、わたしなんかの代わりに怒ってくれて、ありがとう」
彼女は自己評価が低すぎる、とジムノは思う。
「……僕も悔しかったんだ。君の厚意が……平気で踏みにじられて」
だが彼女は自嘲気味に笑い、かぶりを振った。
「わたしはね、きっとジムノくんが思ってるよりも自分勝手だよ」
自分勝手。あまりに彼女に似つかわしくない言葉に聞こえる。
「わたしはあの人たちのために助けたんじゃない。厚意なんかじゃない。ただ自分が嫌な思いをしないために、罪悪感を感じないために……ああしただけ。……自分でそう自覚してるのに、ジムノくんが怒ってくれて嬉しいって思っちゃうような、それに甘えたくなっちゃうような、自分勝手」
「……それを自分勝手と呼ぶのなら、人間はそもそも自分勝手な生き物でしかないんじゃないか。……それに、君がどういう意図だろうと、彼女らが君に助けられたのは事実だ。それなのにああやって恩を仇で返すような真似を……」
彼はそう言い募り、途中で止める。
こんなにも他人の言動にいらいらして、その感情が上手くコントロールできないことに気が付いて。
自分は何を言われようと無視できるというのに、彼女が理不尽な扱いを受けることに耐えられない。許容できない。
唇を噛む彼の顔を覗き込んで、ルエリシアは嬉しそうに、にっこりと笑った。
「わたしは、ジムノくんがそう言ってくれるだけで充分……ううん、すごく嬉しいよ。……きっと、あの人たちにお礼を言われたりするより、何倍も。……だから、ありがとう」
幸せそうな笑顔。
自分なんかが彼女の心を少しでも軽くできているのか、と思うと、たまらなく苦しく、嬉しくなった。
「……ところでさ」
女子生徒たちが道玄坂を下っていったのでその後を追うような気にはなれず、結局南側――桜ヶ丘方面を探索することにした彼らは、拠点とは別のコンビニを見つけていた。
消費期限の少し怪しい弁当の蓋を剥がしながらルエリシアは首を傾げ、ジムノに問う。
「どうしてそこまで嫌われるの?」
ストレートな質問に、ジムノは紙パック入りのぬるい紅茶を無理矢理喉に流し込んでから、そうだな、と少し考える。
水分で胃の気持ち悪さが薄まったのか、多少はすっきりした。
――日頃の行いと言ってしまっても何だが、色々なものの積み重ねでしかなく、まともに話すと長くなりそうだ。
「……僕は、幼い頃からずっと剣道をやっていたんだ」
とりあえずそう切り出す。きっかけはそこだったと思っている。
「最初だけは好きでやっていた。兄や姉の真似をしたくて始めただけ、なんだけどな」
ルエリシアはハイペースで弁当の中身を頬張りながら、うんうんと頷く。
「何も知らずに始めたが……幸か不幸か、相当才能があったらしい。ほとんど努力をするようなこともなく、同年代どころか、いくつも上の先輩……ついには、師範にも勝てるようになっていた」
「へえ」
「まず、それだけで嫌われるには充分だった」
ルエリシアは割り箸を持った手をぴたりと止めた。
「……嫉妬?」
「そうだろうな。すぐに嫌がらせを受けるようになり、最初に通ったところは結局やめてしまった」
「そんな……」
彼女はまるで自分のことのように、悲しげに呟く。
「……だが、あとは……そこから脱することのできなかった自分のせいでもある。何をしてもどこへ行っても恨みや妬みを買い、しかし僕は諦めた。それを覆す努力をしようと思わなかった。ただ……それだけだ」
「それだけ、って……。それにしたって、どうして……誰も分かってくれないの?」
「……スケープゴート、だろ」
ルエリシアは残った白米と揚げ物をまとめて飲み込んでから、首を傾げた。
「スケープゴート?」
オウム返しに問う彼女は、牛乳のパックを手に取る。
さすがに常温で丸二日放置された牛乳はやめておけとそれを取り上げてから、ジムノはひとつ溜息を吐いた。
「標的を一人用意しておけばあとは丸く収まる、ってことだ。……本心で僕のことをどう思っているかは問題じゃない。ただ、周囲に同調して、最低でも僕のことを遠ざけておけば僕と同じ目には遭わなくて済むんだから、皆そうするだけの話だ」
「そんなのって……」
代わりに手に取ったジュースを開けながら、ルエリシアは悔しそうに小さく唇を噛む。
「で、教師だって可愛げのない僕のことは気に入らないわけだし、それを黙認しておけば他には何事も起こらず平和、というわけだ。……まあ……こんな状況になった以上、もう終わったことだが」
そう話を終わらせようとすると、急に手を引かれた。
ルエリシアが真剣な表情で彼の手を握りしめていて、どきりとする。
「……ルエリシア?」
「わたしは……わたしは絶対、そんなこと、しないから。ちゃんと味方でいるからね?」
だから、と言葉を継ぐ。
彼よりも随分小さな手は暖かくて柔らかくて、その感触が心地良くて少しだけ握り返してみると、さらにぎゅうっと握ってきて。
ただそれだけで、今までの苦痛なんてすべて癒されるような気がした。
幸せだ、と思えた。
「だから……。……って、え? どうして笑ってるの?」
言われて初めて、やたらと頬が緩んでいることを自覚する。
引き締めてみようと思ったが無理そうだ。
「……君がそう言ってくれて嬉しいんだ。過去のことなんてどうでもよくなってきた」
自分のあまりの単純さに驚いているが、そう思ってしまったものは仕方がない、と開き直る。
「でも……」
「本当に、いいんだ。……ありがとう」
そう伝えると、ようやく彼女は少し安心したように微笑んだ。
その表情にジムノもまた安心してしまう。
「……あ」
気が抜けたことで、ひとつ思い出したことがあった。
「そうだ。剣道……学校といえば。確か、ロッカーに木刀を置いてあるな」
唐突に少し変わった話題に、ルエリシアは一瞬きょとんとしてから、
「あ……武器になるかもってこと? 取りに行く?」
と首を傾げた。
「そうだな……」
言ってはみたものの、少し迷う。
わざわざ取りに行かずともその辺りに転がる瓦礫から長柄になりそうなものを見つけ出すこともできるだろうし、学校へ行ってみることでどれだけのリスクがあるか分からない――とはいえ、それはどこに行くにしろ同じだが。
もちろん手に馴染む木刀が最も使い勝手が良いだろうし、学校であるからには避難所のようになっているかもしれないという期待もなくはない。
「渋谷駅から通ってたならそんなに遠くないよね? わたし、行ってみたいなあ」
「まあ、ここからなら……何事もなければ五分から十分、というところか。……行ってみたい、のか?」
少し楽しそうに言うルエリシアに首を傾げる。
「ジムノくんの通ってたところ、見てみたいし。それに、わたしはそもそも高校ってほとんど見たことないし……」
「……そうか。それなら、行ってみようか」
「うん!」
「地図があると分かりやすいね」
ルエリシアは、ジムノの広げた紙の地図を覗き込む。
拠点のコンビニにはなかった住宅地図を拝借し、必要そうな情報を書き込みながら進むことにしたのだ。
電子機器もインターネットも使えない以上、自分たちの目で確認していかなければ何の情報も得られない。
「ああ。しかし……」
巨木に塞がれて通れない道に目印を丁寧に書き入れてから、ジムノは溜息を吐く。
「……死体が多いな」
「……うん」
最初に化け物が現れて丸二日。彼らと同じようにどこかに息を潜めて化け物から逃れ消えずに済んだ人間もいたようだが、当然そのまま一歩も外に出ず隠れ続ければ飢え死ぬ。水か食糧か、あるいは助けを求めて外に出てきたところを殺されたのであろう死体が所々に転がっていた。学校に近づくほどに、見慣れた制服を着た死体も増えている。
最初のうちは見かけるたびにまだ息がないかと確認していたのだが、そのうち近づかずとも死んでいるのだと理解できるようになってきた。
今日はまだ化け物には出くわしていないが、いつどこで何が現れるか分かったものではない。
いつだって自分たちがここに転がることになる可能性はある。何度も自分にそう言い聞かせ、ジムノは警戒を緩めないよう必死で意識していた。
特に、最初に見た大型の化け物にだけは遭遇したくない。
「あれが学校?」
地図と眼前の景色を何度も見比べながら、ルエリシアが声を上げる。
比較的見通しの良い道の先、道路から生えだした樹木や傾き倒れかけた信号機の向こうに、確かに見慣れた校舎の一部が顔を覗かせていた。
「ああ」
木の根に押し上げられひび割れた歩道が時々ぐらつく。躓きそうになったルエリシアに手を差し伸べると、にっこり笑って握ってくれた。
「ありがとう」
「……ん」
嬉しそうな表情を直視できず、ジムノは学校へと視線を移す。
そこも例に漏れず、二日前とはすっかり様変わりしていた。
植え込みはひっくり返されたかのように破壊され、元々生えていたはずの木が倒れ新たに生えてきた木に押しやられ。
校門は誰かが一度閉めたらしいが、鉄でできているはずのそれはひしゃげ潰され転がっていた。
「……」
兎や蛙の仕業ではなさそうだ、と彼は思う。
さすがにそこまでの力はないだろうし、そもそもあの体のサイズなら骨組みだけの門をわざわざ潰してゆく必要などない。
「何がいるか分からない。気を付けろ」
「……うん」
尚更早く木刀を回収したくなってきた。
彼はまっすぐ教室へと向かうことにする。
慎重に敷地内へと足を踏み入れぐるりと見回すと、外と同様に酷い有り様だった。街の中と同様に木々が生え出し、赤い花がそこかしこに咲き、校舎は所々が崩れている。
とはいえ彼には感慨も何もない。上半分の崩壊が目立つ校舎へさっさと足を踏み入れ、近くの階段から四階の教室を目指す。
やはり樹海化以前に死んだ人間は消えているのか、不自然なほどに死体も血の跡も見当たらなかった。
ただ、街中の風景に比べると、妙に建物に対する破壊の跡が目立つ。
穴が開いた壁、ガラスがほとんど吹き飛んで枠だけになった窓、焦げた床、紙くずのようにひしゃげた扉。
ルエリシアもそれが気になったのか、少し不安げな表情を浮かべた。
「……何が……あったの?」
「おそらくは、僕が最初に見た巨大な化け物の仕業だろうな」
ジムノは周囲に視線を配りながら答える。
自分の教室に近づくほどに、破壊の跡は酷くなっていた。
あの化け物はあのまま侵入しこの校舎を蹂躙していったのではないだろうか、と彼は想像する。
「……ここだ」
そうしているうちに、ほんの一昨日まで毎日数時間を過ごしていた教室の前へと辿り着いた。
「わっ……」
ルエリシアが背後で小さく声を上げる。
その教室は今まで見たどこよりも大きく破壊されていた。
窓側の壁はもはや完全に崩れ落ちており、廊下側の壁も用を成していない。机や椅子は外に払い落とされたのか三分の一ほどしか残っていなかった。天井も床も崩落しそうな頼りなさがあり、足を踏み入れるのには少し勇気が必要だ。
とはいえ、ジムノが使っていたロッカーは廊下側だったのが幸いだった。教室の後ろにぎっしりと並んだロッカーの扉はやや歪んでいたものの問題なく開き、彼は木刀の入った袋を取り出す。
何か他に役に立ちそうなものはあっただろうかと一昨日の通学に使った鞄も引きずり出してみるが、記憶通りほとんど空だった。教科書や筆記用具すらも机とともにどこかに消え、こうなった今では何の役にも立たないであろう財布と電車の中で読むために持ち歩いていた文庫本だけが底に残されている。
彼は小さく溜息を吐き、鞄からそれらを取り出すこともなくロッカーに突っ込み直した。
「……あれ、何か落ちたよ?」
ルエリシアがそう言って拾い上げたのは彼の定期入れだった。
鞄の外ポケットに入れていたのが弾みで落ちたらしい。
「あっ……」
声を上げるが既に遅く、彼女は電車の定期券に重ねて入れていた学生証に見入っていた。
写真に所属とフルネームが添えられたそれをたっぷり数秒眺めてから、ふふっと笑う。
「機嫌悪そうな顔してる」
はい、とその定期入れを渡された。
自分でも改めてその写真を見て、少し笑ってしまう。
その写真は入学直後に撮ったのを覚えている。彼女の言う通り、あの時は確かに機嫌が悪かった。
新しい環境に行くことで何かが変わるだろうかと思ったが、全くそんなことはなかったのだから。結局またこんなところで三年間も過ごすのか、とうんざりしていた。
その時だけではない。一昨日までずっとそんな気分だったはずなのに、今はこれをまるで他人事のように見ることができていることに気付き、妙にすっきりした。
「ありがとう」
受け取った定期入れをロッカーに放り込んで歪んだ扉を閉める。
もうこれは必要ない。
木刀の入った袋だけを提げ、元来た道を引き返す。
瓦礫をできるだけ避けて歩きながら、ジムノは呟いた。
「……しかし、何も聞かないんだな」
「え?」
ルエリシアも後ろで同じように歩きながら、きょとんとしたような声で聞き返してくる。
「さっきの……学生証」
我ながら回りくどい、と思いつつもそう答えた。
――彼は、ルエリシアに本名を名乗っていない。
彼女はそれを知ったはずなのだ。
写真しか見なかったのだろうか、とも思ったが、ルエリシアはしばらく考えてから、
「さっきの……? うーん……?……ああ、もしかして、名前の話?」
と口にした。
気付きはしても気にはしなかったらしい。
「……ああ。その……。別に、騙すつもりがあったとか、君を信じていなかったとか、そういうわけでは……なくて」
まさか気にされていなかったとは思わず、やたらと言い訳がましく答えてしまう。
「えっ? 分かってるよ、そんなの。でも、どうして?」
パリン、と音を立ててガラスの破片を踏み抜いた。
不審がられるのが怖かったのだ、と自分で気付く。分かってる、と当然のように言われて妙に安心してしまった。
「深い意味はないんだが」
彼は、ムラサメトキノ、という自分の名前が嫌いだ。
名前そのものが、というよりは、その名に紐付けられた自分自身が嫌いだった。呼ばれる度、他人に嫌われる自分に、自分が嫌いな自分に、黒く重く塗り潰されるような感覚があって、酷く息苦しく感じていた。
幼い頃、あまりにも名前を嫌がる彼を見かねた姉が愛称で呼ぶようにしてくれて、それ以来、家ではそれで通していたのだ。
嫌いな自分でいたくなくて、ルエリシアにはその愛称で名乗った。
それをかいつまんで説明すると、彼女は「そっか」と優しく答える。
「ちょっと嬉しいな」
「?……何故だ?」
背後で弾む声に、足元から視線を外さないままで問い返す。
「だって、家族が呼ぶための名前で名乗ってくれたんでしょ? 最初から信頼してくれてたんだな、って」
「……」
そう言い直されるとなんだか気恥ずかしくて、動揺してしまう。
細かな瓦礫に足を滑らせそうになり、慌てて踏みとどまった。
「わ、大丈夫?」
「ああ。……ええと……ありがとう」
肩越しに振り向くと、ルエリシアは「うん?」と疑問符混じりに頷く。
彼はそれには答えず、また慎重に歩き始めた。
「……誰か、いるかもしれない」
保健室の棚を調べたジムノはそう呟いた。
「えっ、本当?」
「目ぼしい薬や応急手当の道具がほとんどなくなっているんだ。そのあたりに転がっているわけでもなさそうだし。一昨日……最初の襲撃では悠長にここに駆け込む余裕なんてなかっただろうから、状況が落ち着いた後に誰かが回収していったと考えるのが自然だ」
四階の教室ほど酷くはないが、ここも外に面した壁は破壊され、床の半分は瓦礫に埋まっていた。
「そっか……。……って、ジムノくん、足元。……床に血が付いてる」
ルエリシアの声に釣られて下を見ると、確かに赤い血が数滴垂れ落ちた跡が残っていた。
「……!」
それもまだ乾ききっていない。
「これが人間のものだと仮定すると、だが……。ここに死体が転がっていないということは、手当てした後についでに薬や道具なんかの物資を持ってここから移動できる程度の元気はあった、ということになるな」
「……じゃあ、もしかして、近くにいるかもしれない?」
「ああ。危険を冒してまでここに来るということは、重傷ではなくとも、放っておけば治るかすり傷というわけでもないんだろう。それならあまり遠くに移動しているとは考え難い。……まあ、今生きているとも限らないが」
今朝酷い光景を見てきたばかりだ。ルエリシアにもあまり期待させたくなかった。
「……うん……そうだね。でも……」
口ごもる彼女の様子に苦笑する。
「探しに行きたいんだろう?」
「……いいの?」
「構わない。……だが、どこかに化け物もいるかもしれない。危険を感じたらすぐに撤退だ」
それに彼女は真剣な顔で頷いた。
「うん……わかった」
仮に避難所になっているとすれば、と真っ先に覗いてみた体育館はどうやらハズレのようで、がらんとした空間にただただ静寂が落ちていた。
「わあ……広い」
体育館という空間を見慣れていないのか、ルエリシアの上げた感嘆の声が少しだけ響く。
他の場所に比べると破壊の跡は少ないのだが、誰かが避難してきていたような痕跡すらない。さっさと次を当たろうと踵を返した、その瞬間。
かたん、と奥から小さな物音が響いた。
「――っ!」
ジムノは咄嗟に右手でルエリシアの腕を引き、左手で袋に入ったままの木刀を構える。
しかし――
「おい、こっちだ!」
音の聞こえた方向、舞台の横にある扉が少し開くと、一人の男が顔を覗かせた。
ジムノとルエリシアは思わず視線を交わし、どちらからともなく頷き合う。
信用できる相手とは限らない。警戒は解かずに土足のまま体育館に踏み込み、男の様子を伺いながらそちらに近付く。
「良かった、まだ生き残りが……。……ん?」
その男はぼさぼさの茶髪頭にバンダナを巻き付け、よれたシャツにジーパンというラフな姿で、ふと目を見開いた。
「ちょっ……お前……もしかして、ムラサメか!?……つっても、お前がオレのことなんか覚えてるわけねえか……」
そう苦い表情を浮かべる男の顔は、しかしその言葉に反してジムノにも見覚えがあった。
「……いえ……ハジメ先輩?」
クラスメイトすら覚える気がないジムノが珍しく覚えていたその男は、頭を掻いてやや気まずそうに頷いた。
「お、おう……。とにかく中に入ってくれ」
外じゃ危ない、と彼らを手招きする。
その扉の向こうは体育倉庫だ。足を踏み入れた瞬間、独特の臭いが鼻をつく。半分地下室であるためか、少し湿った空気が肌にまとわりついてきた。
「ええと……おじゃまします?」
ルエリシアもおずおずと後に続く。
男は扉を閉めると内鍵をかけた。
窓のない体育倉庫の中は、大きな懐中電灯で煌々と照らされていた。警備室から持ってきたらしい簡単な武器や防具、保存食の残骸やペットボトル、薬や包帯などが辺りに転がっている。
「あー……ええと」
男はしどろもどろに何か言おうとして、しかし言葉にならない。
ジムノも何と言えばいいか分からず、気まずい沈黙が落ちた。
それにルエリシアもまた少し気まずそうに、
「知り合い……なんだよね?」
と小さな声でジムノに問う。
少し前に、誰からも嫌われる話をしたばかりだった。今朝には実際に嫌な思いもしている。それを意識しているのか、彼女は男を警戒するようにジムノの服の裾をぎゅっと握りしめている。
「剣道部の元主将。今年卒業した先輩だ」
「……おう。ハジメユウセイってんだ」
「あ……ルエリシアです。よろしくお願いします、ユウセイさん」
まだ強張った顔で、それでも彼女は小さく頭を下げる。
適当に座ってくれや、とユウセイは二人に勧め、自身も手近なマットの上に腰を下ろした。
「……先輩は、どうしてここに?」
居心地の悪さのせいで腰を落ち着けられるような気分でもなかったが、少し疲れたのは確かだ。勧められるままに座り込み、ジムノは不信感を隠さずそう尋ねる。
ルエリシアも彼の隣にちょこんと座った。
「偶然な。一昨日はちょいと用事があって久々にここに来てて、そのまま成り行きで……って感じだ。……お前は? この二日間見かけなかったが、校内にいたか?」
「いえ。今日はこれを取りに戻ってきていただけで」
問い返され、片手に携えたままの木刀を視線で示し答える。
「おいおい、この状況で外を歩き回ってんのかよ。よく生きてんな」
ユウセイは呆れたように息を吐いた。
「……ユウセイさんは、ずっとここに一人でいたんですか?」
「いんや……最初は何人かいたんだけどな……たった二日でどんどん減っちまって、ついに今はオレ一人、ってわけだ」
ルエリシアの問いに、ユウセイは自嘲めいた笑みで答える。
「……ま、身体は鍛えておくモンだな。オレもお前もとりあえずは死なずに済んで……いてて」
何気なく姿勢を変えようとした彼は唐突に呻いた。
それにルエリシアは思い出したようにはっとして声を上げる。
「そ、そうだ! わたしたち、ケガした人を探してて……。もしかしてユウセイさん、どこかケガを?」
「ああ……ちょっとヘマしちまってな。つっても別に大したことはねぇよ」
それがどうかしたか、と訝しげな表情。
「見せてもらってもいいですか?」
「あん? まあ、別にいいけどよ……」
彼がシャツを脱ぐと、腹に血の滲んだ包帯が何重にも巻かれており、ルエリシアは息を呑んだ。
「あー、どうせそろそろ包帯変えなきゃいけねえな、こりゃ」
そう言いながらユウセイは手近に転がっている新しい包帯を手に取ろうとするが、彼女はそれを止める。
「待ってください。あの……わたし、治療できますから」
「……治療?」
「はい。……包帯、外してもいいですか?」
真剣な表情の彼女にユウセイは少し慌てて、自分でやる、と言って包帯を剥がし取る。
包帯に隠れていた傷は左の脇腹にあり、ようやく血が止まりかけているところ、といった様子だった。
まるで刃物にでも切られたような傷は十五センチほどはあり、ルエリシアは青ざめた。黙って見ていたジムノも少しだけ顔を顰める。
「お、大怪我じゃないですか……!」
「いやいや、ちょいと派手だがかすって表面をやられただけで、内臓までは達してねえみたいだし。しかし治療って……」
「とにかく横になってくださいっ!」
有無を言わさずきっぱりと言われ、ユウセイはその勢いに押されるようにおとなしくその場に横になった。ルエリシアはさっさと脇に移動し、傷口に手をかざす。
彼の言う通り傷は深くはなかったのか、見る間に塞がってゆく。
早送りの映像のようなその様子に、彼は目を丸くした。
「お、おお……?」
彼の反応に対して身構えるように、治療を終えたルエリシアはほんの少しだけ身を縮める。ジムノもまた彼の様子を注視していたが、二人の心配は杞憂に終わった。
「す、すっげえ! なんだコレ!?」
ユウセイは飛び起き、傷のあった場所を触ったりつまんだりしながらしきりに驚きの声を上げる。
「おい、マジで? ホントに治ってんじゃねえか。痛みも消えてる。すげえ。すげえな、お前!」
「え、あ、ありがとう……ございます……?」
予想外の反応だったらしくルエリシアは戸惑った様子で応えた。
「いやいや、オレの方こそありがとな! 助かったぜ」
彼女は安心したように少し微笑むと、またジムノの隣に座り直す。
「すげえ力だな。超能力、みたいなもんか?」
「ええ、まあ……。……ふわあ」
彼女は答えてから大きな欠伸をして、眠たそうな目を擦った。
そういえば結局昨晩は彼女はほとんど眠っていないはずで、能力を使ったことで急激に眠気に襲われたのかもしれない。
「ルエリシア」
「んー……ふあ……うん。ちょっと眠たいだけ……だよ……」
ジムノの呼びかけにもうつらうつらとしながら答えてから、こてんと彼にもたれかかるように倒れ込んできた。
「お、おい。大丈夫なのか?」
そのまま眠りに落ちてしまった彼女を見て、ユウセイは不安げに声を上げる。
「ええ、まあ……あの力は体力を消耗するので、疲れて眠ってしまっただけです」
ジムノの答えに、そうか、と彼は肩の力を抜いた。思い出したようにシャツを着直す。
「すみませんが、しばらくここで休ませてもらっても?」
「ああ、もちろんだ。つーか、とりあえず今日はここに泊まってけよ。さすがに暗くなってからウロつきゃしねえだろ?」
確かに、明るいうちに彼女が目を覚ますこともなさそうだ。
「……それじゃあ、お言葉に甘えて」
そう答えてから、ジムノは彼にしがみつくようにしながら眠っているルエリシアの身体をその場に横たえてやった。それでもまだ寝ぼけたようなふわふわとした動きで彼の手から離れまいとくっついてきて、それに思わず頬が緩んでしまう。
「……お前って、そんな顔もするんだな」
「はっ?」
ひっくり返った声を上げてしまい、それにユウセイは笑った。
「ははっ。いや……あー、なんだ。……お前には、謝らなきゃな」
「謝る?」
ジムノがオウム返しに問うと、苦笑が返ってくる。
「ほら……お前が入部してきて最初の試合だよ」
別にジムノに心当たりがなかったわけではなく謝られる必要を感じていなかっただけなのだが、黙って聞く。ルエリシアを引き剥がすことは諦め、握られた手の体温を感じながら、彼女の首元まで隠れるように手近に転がっていた毛布をかけてやる。
「オレにとっては高校最後の試合だった。だから……入部してきたばっかりのお前に、オレがやるはずだった団体戦の大将の座を奪われたときも、個人戦の決勝で負けたときも……お前には酷い態度を取っちまった。実力勝負の世界なんだから、お前は何も悪くないってのに」
「……しかし、それは僕の態度にだって問題が……」
「……自覚あったのかよ。……けど、それでも、オレはあの部の主将だった。個人の感情でお前を認めないような真似はしちゃいけなかったんだ。お前の態度がどうだっていうならそれを正してやるくらいのつもりじゃなきゃいけなかった。オレがお前を詰るのに便乗してくる同級生や後輩どもを叱りつけなきゃいけなかった。理不尽なことを言うコーチからお前を守らなきゃいけなかった。……こんなんじゃ剣道部失格だ、って……気付いたのは、部も引退した後で、お前が部どころか校内で孤立してて、もうどうにもならなくなってた時だった」
剣道はスポーツであると同時に、心を重視される武道だ。礼儀を欠いているとみなされれば反則扱いになるほどの。
だがジムノにとっては、剣道は好きでやっていたわけですらなく、生きていくために使っていたツールの一つでしかない。例えば、家から離れた私立高校に金銭的不安を抱えることなく通うため、だとか。そのために使えるのがたまたま剣道だっただけの話だ。礼儀など、試合で必要な最低限を演じられれば問題なかった。だから他人にも求めない。
「……それを言うならあの部に剣道をするにふさわしい人間などいなかったことになりますし……。そこはお互い様というか、先輩がそこまで思い詰める必要もないと思いますが」
ジムノがやや怪訝な顔でそう言うと、ユウセイもまた似たような表情を浮かべた。
「……お前、オレを恨んでないのかよ?」
「いえ、別に」
確かにユウセイの言動がきっかけの一つだったのかもしれないが、おそらく彼がいなくとも同じようなことになっていただろうとジムノは思っているし、この二日間で、過去のことなどどうでもよくなりつつある。
「……そうか。でもよ、オレが悪かったんだなって気付いたとき、オレはもう一つ過ちを犯した。そのときにお前には謝りに行くべきだった。お前が気にしていようとなかろうとな。それなのに受験だの何だのって自分に言い訳して、そのまま卒業しちまった。こんな時になって偶然会えたのは、まあそういう縁だと思うんだよな。だから、オレの自己満足かもしれないけど、謝らせてくれ。あの時は悪かった。今更何の取り返しもつかないから……許せとは言わねえが」
だから謝る必要などないというのに、と内心呟き、ジムノはルエリシアに視線を落とした。すっかり熟睡しているらしい彼女はゆるやかな寝息を立てている。
こんな風に謝られるのは初めてだが、おそらく、ユウセイの言うタイミングで謝られても、きっとそれを受け取ることはできなかったのではないだろうか、と思う。だが、今は。
ジムノは顔を上げる。
「……いえ……許すも何も、本当に先輩のことは恨んでいません。それに、僕に今まで何も言わなかったのも間違っていないでしょう。僕に話しかけたなんて――まして謝ったなんて知れれば、先輩まで疎外されていたでしょうし」
そう答えると、ユウセイは苦笑した。
「あー……はは。そうか。なんつーか……勿体ないことしたな、オレ」
「?」
意味が分からず怪訝な視線だけで問うジムノに、彼は頭を掻いて答える。
「いや、オレたちって……顔を合わせたのはお前が入部してからオレが引退するまでの三ヶ月間くらいしかなかったけどよ……オレが知ってるお前は、何をしても何を言っても無表情で、必要最低限のことしか喋らねぇで、ただ剣道はめちゃくちゃ強い上にどうやら勉強もめちゃくちゃデキるらしい、っていう……機械みたいな奴だった」
でもよ、と彼は笑う。
「最初からもっとお前のことを知ろうとすりゃ良かったな、って思ったんだよ。お前がそんな優しい奴だなんて知らなかったし、恋人に笑いかけて手を握ってやってるとこなんて想像も付かなかった」
「こ……っ!? いや、ち、違います、そのっ、ルエリシアは……ええと、この混乱で出会った……だけで……」
恋人、という単語に酷く動揺し、ジムノは裏返りかけた声で否定し、否定している自分の言葉で悲しくなってきて、結局途中で止めた。
「はははっ、そんなことでそこまで慌てる奴だとも思ってなかった。……そうかそうか、片思いか」
体温が数度上がったように感じる。
「……ええと……。……その」
「それは否定しねーんだな。……つーか、そんなこと言われても真顔でイエスかノーかで答えるような奴だとも思ってたし、いや、そもそも他人に興味なんてない奴なんだと思ってたから、本当に……オレ、お前のこと何にも分かってなかったな」
「……僕がそう振る舞っていたのだから、むしろ的確に評価されているように思いますけど」
「ちげーよ、そういうことじゃなくて……お前は心を開きたくなくてそうしてたんだろ。だから、心を開けるようにしてやれりゃ良かった、って話だよ。ほんと、悪いことしちまった。お前にも、オレに釣られてお前を遠ざけちまったみんなにも」
ユウセイは心からそう後悔しているようだった。
「オレだけが悪いわけじゃないとしたってよ、言わなきゃよかったことも、言わなきゃならなかったことも、確かにあったんだ。……それも、もしかしたら、一昨日までならやり直せたかもしれねぇ。たとえたった一日でも、数時間でもな」
そう言って、ユウセイは右手を差し出してきた。
「……」
「何だよ、その顔。……今更何を言ったって手遅れなのは分かってるけどよ。お前が嫌じゃなけりゃ、せめてこの場は……できるなら、これから、上手くやっていきてぇんだよ」
恨んでいないことと信用していいかどうかは別物だ。
ジムノはしばらく差し出された手を見つめて、しかし、きっとルエリシアならこの手を取るのだろう、と思い至る。
「わかりました」
だからそう答えて、彼もまた右手を差し出した。
「しっかし……これからどうするかねえ」
ユウセイは背中を丸めて自分の膝に頬杖をつき、苦笑した。
「ワケわかんねーことが多すぎて、どうすべきか……っつーか、自分がどうしたいのかも決めにくくてよ」
「……どうしたいか、とは?」
問い返したジムノに、ユウセイは少しだけ口ごもってから、迷うような視線を向ける。
「……オレさ、実は就職も進学も失敗してよ。卒業してからもしばらくフラフラ遊び歩いたり、引きこもったり、まあ気が向いたときに就職活動したりしてたワケだ」
ジムノは黙って聞く。
「で、ほんの三日前に、ようやく内定を貰ったとこだったんだよ。……そんで学校に報告に来たところにコレだ」
はは、とユウセイは力なく笑う。
「学校でほどほどに勉強して、別に働きたかねーけどそういうワケにもいかねーから就職して、で、これからはそこで働いて、得た金で好きなこともして、そのうち相手がいりゃあ結婚とかもして……って、まあそういう……無難な人生を送ることになるんだろうなって考えてたワケだ」
疲れた声。
「なのに、そんな……どうってことない将来も、これまで積み上げてきたモンも、何もかもがあっという間になくなっちまった。仮に、今この瞬間にあの化け物どもが全部消え失せてくれるとしても、もうオレたちの知ってた世界は終わりだ。そうだろ?」
おそらくは大多数の人間が死に絶えた。彼の言う通り、もう世界が元の形を取り戻すことはないのだろうとジムノも思う。
「だから、さっきの、自分がどうしたいのか、ってのはさ……。生き残ることに意味があるのか、ってことだよ」
「……」
ユウセイはひとつ息を吐いてから、マットの上に身体を倒した。
「何もかもが一瞬で消えて、命だけ残って。いつ化け物に殺されるかに怯えながら、二日前までの世界に残った食い物とか探して、何のインフラもねえ不便な生活して。そこまでして生きて何の意味があるんだ、って考えちまう。いつどんな殺され方をするかも分かんねえし、食い物だっていつまでも何でも食えるわけじゃねえ」
――もし今一人でいたらそう考えていただろうな、とジムノは思った。
ユウセイの言う通りなのだ。希望なんて一つもない。
だが。
そんな希望のない世界でも、隣にルエリシアがいてくれるなら少しでも長く生きていたい、と彼は思ってしまったのだ。今は生き延びる意味なんてそれだけで充分だと思える。
だが彼には、二日前まではそれすらもなかった。
誰かに手を伸ばしてもらえることもなくて、自分から手を伸ばしても拒否されて。そんな世界で生き続けるのは苦痛でしかないと、ずっと思っていた。死にたいとまでは言わずとも、生きたくなかった。消えたかった。
「……介錯でもしましょうか」
ぽつりと呟くと、ユウセイはがばっと勢いよく身を起こした。
「っ……。……はは。お前、意外と……コワい冗談言うんだな……。……冗談、だよな?」
「……まあ、確かに本気ではありませんけど。……介錯して欲しかったのは僕ですよ。二日前までは、ですが」
ユウセイは気まずげに目を逸らす。
「だから、悪かったって……」
「……謝る必要はありませんって。そういう話ではなく……」
また面倒な話が続きそうだったのでそう言うと、ユウセイは少しだけ沈黙してから、
「ん?……ああ……なるほど。好きな女でも作れば生きたくなるって?」
と、ニヤニヤ笑ってみせた。
「……っ! 違……わなくは……ないですけど……」
「はは。だけど、そうなんだよ。そういう……生きる理由、ってやつ。……今までわざわざ考えたこともなかったんだよな」
彼はまたごろりと寝転がった。
「まあ毎日それなりに楽しくやってたつもりだけどな。これがないとオレはダメだ、これのためなら生きられる、ってモンはなかったんだよ」
くすんだ天井を見つめて彼はぼんやりとした口調でこぼす。
「剣道は好きでやってたけどよ、別に剣道じゃなくとも……サッカーだろうが野球だろうがそれなりに熱中してやれたと思う。テレビ見てマンガ読んでゲームして、ってのも好きだけど、なくても死にゃしねえ。家族やダチは……もちろんすげえ大事なんだけどな、死んじまったらどうしようもねえし、って……ま、ある程度は割り切れる。どれも、生きる理由って言うほど大層なモンじゃねえ」
なのに、と口元だけで彼は笑う。
「それがいっぺんに全部消えちまったら……こんなにも……。……いや」
言葉を止めて、彼はひとつ溜息を吐いた。
「そんなこと言ってても仕方ねえな。別に死にたいわけじゃねえし、今はやれるだけのことをやるしかねえか」
ってことで、と彼はひとつ伸びをする。そのままひとつ大きな欠伸をして、ああ、と思い出したように声を上げた。
「そういやオレ、昨日からほとんど寝てねーんだわ。悪いけどしばらく寝かせてくれねえか?」
「……。……これからどうするか、って話じゃありませんでしたか?」
「んー……まあ、どうせ行動するのは明日からだし、急ぐ必要もねえだろ。起きてから考えようぜ」
ユウセイはそう呑気に言うと、もう一度欠伸をして目を閉じる。よほど疲れていたのか、ほんの数秒でいびきをかき始めた。
「……まったく……いい加減な」
そう呟いてから、改めて、ユウセイを本当に信用していいものかどうか考える。
裏切るとか裏切らないとか、ただそれだけの問題だけではない。悪意がなくとも、彼の判断や能力を信じて危機に陥るようなことがあっては困るのだ。
最初は数人で行動していたのが今やユウセイひとりになってしまっている、という話だけでも充分に不安だ。
だが、この状況で彼だけでも丸二日間生き延びているというのもまた事実であり、ある程度は力になると考えてよいのかもしれない、とも思う。
「……ん……」
つらつらと考えていると、隣ですっかり眠り込んだルエリシアから小さな声が漏れた。
安心しきった寝顔でもぞもぞと寝返りを打つ姿に、つい顔が緩む。
少しずれた毛布を掛け直してやり、彼はその隣に横になってみた。
薄い桃色の肌に長い睫毛、僅かに開いた唇から漏れる寝息までもが愛おしく感じる。空いた手をほとんど無意識に伸ばしそうになって、慌てて引っ込めた。代わりに、ずっと握られたままだった手をしっかりと握り返す。混じり合う体温に、心臓がぎゅっと苦しくなる。
ほんの短い時間を共に過ごしただけの他人にこんなにも強く惹かれるなんて、想像したこともなかった。乾いた砂漠に水を撒かれたように、熱いコーヒーに砂糖を入れられたように、自分の意思ではコントロールできないほどに強く急速に、自分の世界が侵される。変質する。だがそれは身を任せたくなるほどに心地良い。
「……生きる理由、ね」
そんな言葉にするとくすぐったいが、彼女の存在は間違いなくそれだ。もし彼女に出会えていなければ自分は今頃どうしているのだろうか、と考えると怖くなる。少なくとも、この絶望的な状況をこんなにも幸せな気分で過ごしていることなど有り得なかっただろう。他人を信じるかどうか、など真剣に考える価値すらないと切り捨てていたに違いない。――その自分は、きっとそんなことを怖いとは思いもしないのだろうが。
時間を潰せるものもなく、外の物音さえほとんど聞こえない体育倉庫の中はとにかく退屈だった。
横になっていると眠ってしまいそうで困る。時折立ち上がって身体を伸ばしてまた座り直して、とただ繰り返していた。所狭しと詰め込まれたボールの籠や得点板、丸められたネットなどの山を眺めていても、不愉快な記憶が過ってゆくばかりだ。
ジムノが学校生活で最も嫌いなのが体育の授業だった。個人種目ならまだともかく、チームプレーを求められるのは苦痛で仕方がなかった。真面目にやろうが手を抜こうが敵味方問わず罵声を飛ばされ、絶好の機会とばかりにファウルまがいの接触を繰り返され、教師もそれを咎めない。いちいち気にするのも馬鹿らしくただ感情を殺して時間が過ぎるのを待つばかりだった、とまるで何年も前のことのように思い出す。
「……ジムノくん?」
眠そうな柔らかい声で唐突に呼ばれ、彼ははっとしてルエリシアを見下ろした。
彼女は欠伸をしてから目をこすり、ゆるゆると身体を起こす。
「まだ眠っていて構わないぞ」
彼女が眠り始めて六時間ほどは経ったが、まだ夜は長い。
「ん……でも」
ルエリシアは眠っているユウセイに視線を投げ、それからジムノの顔を見上げてその隣に座り直しながら、少しだけ不安げな表情を浮かべた。
「……どうした?」
「なんだか……変な顔、してたから。……大丈夫?」
「……ああ、いや……何でもない。今となってはどうでもいいことばかりだ」
そう答えるとルエリシアは表情を曇らせたまま、きゅっと手を握ってきた。
少し冷えた柔らかな指先の感触に、心臓が跳ねる。
「あの……ごめんね。ここに来てみたいなんて、わがまま言って」
ジムノはその言葉の意図が読めず、彼女の沈んだ表情を見下ろした。
「やっぱり……いろいろイヤなことも思い出しちゃうだろうし、それに、知ってる人にも会っちゃったし……」
彼女はちらりと視線でユウセイを指し、申し訳なさそうに唇を小さく噛んだ。
「いや。いいんだ、そんなことは」
確かに一人ならわざわざこんなところに足を運ぶこともなかっただろうし、仮にそうしたとしても後悔することになっていたのではないか、と彼は思う。
だが、こうしてルエリシアが隣にいてくれるだけで、世界の見え方がまるで変わったのだ。
不愉快な記憶が他人事のように感じて、何かを切り捨てない選択肢も考えて、彼女の見せてくれる世界をもっと見ていたいと――生きていたいと思うようになって。
「それより、これからのことだが」
そのためなら、自分で前へと手を伸ばせるようになって。
「今日はもうここで夜を明かす。明日から――」
彼もまたちらりと眠ったままのユウセイを一瞥し、
「――彼も一緒に行動しようかと考えている。君はそれでも構わないか?」
そう問うと、ルエリシアは少しだけ驚いたような表情を見せた。
「えっ……。……悪い人じゃなさそうだし、わたしはいいけど……ジムノくんは、いいの?」
「さっき少し話して、僕らを敵視しているわけではないということは分かった。そういう意味では心配しなくていい」
ユウセイの言葉を全面的に信じたというわけではなく、仮に彼から裏切られたところでルエリシアが心配するように傷ついたりはしないという意味だが。
「……そっか。じゃあ、そうしよっか」
「ああ。それなら今後のことは明日彼も交えて話し合うとして……君はまだ眠っているといい。疲れているだろう?」
昼間は何度か力を使って、しかし食事はあまり満足に摂れていないはずだ。せめて睡眠くらいは、と思ってのジムノの言葉に、しかしルエリシアはかぶりを振った。
「それを言うならジムノくんだって昨日の夜中からずっと寝てないでしょ。一度交代しよ?」
「……分かった、ありがとう。じゃあ、僕が起きるまでは頼む」
このまま数時間眠って、もう一度彼女と交代すれば丁度いいくらいだろう。
「ん。何かあったら起こすから、心配しないで」
「ああ」
ジムノはその場に横になる。そこにルエリシアがにこにこしながら自分の使っていた毛布をふわりと掛けてきて、
「――っ!?」
その毛布に残る彼女の体温と甘い匂いに心臓が跳ねた。
「……?」
ルエリシアはきょとんとして首を傾げる。
このまま包まれていられれば幸せなのだろうが、それではとてもではないが眠れそうにない。
「あ、いや、ええと……。少し暑いから、大丈夫だ。これは君が使っているといい」
突き返すのも名残惜しく、また彼女に申し訳なくも思うが、それでもそう告げると彼女はやや不思議そうな顔のまま「そう?」と毛布を自分の膝にかけた。
「じゃあ、ありがと。寒くなったらいつでも言ってね?」
「……ああ」
にっこりと笑った彼女を見上げているのも、このまま目を閉じるのも、少し気恥ずかしい。
ジムノはぐるりと寝返りを打って彼女に背を向け身体を丸めた。