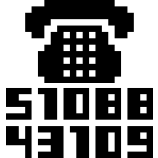ふと二人きりになった病室で。
なんとなく気まずい苦さを含んだ沈黙が落ち、ベッドに上半身を起こした格好のジムノは恐る恐るそう問うた。
「何のこと?」
ルエリシアにはにっこりとそう問い返され、それはいつも通りの彼女に見えるが、どことなくぎこちなさのような、突き放されたような違和感がずきりと沁みる。
「その……。……だ、黙って抜け出してミヅチを倒しに行ったこと……とか……」
つい、自分の膝にかかった白い布団に視線を落としてしまう。
皆が寝静まっている時を狙ってエリシャと二人で抜け出し、ミヅチに挑んだ。挙句の果てに、二人して命を落としかねない重傷を負った。それどころか、ルエリシアが駆けつけてくれるのがあとほんの少しでも遅ければ、今頃は自分たちどころか、彼女も、世界すらも、どうなっていたか分からない。
具体的な言葉として口にすると、改めて、とんでもないことをしてしまったと自覚する。結果としてはこうして辛うじて生きて帰ってこれたものの、紙一重だった。
ずきずきと心臓が痛むが、自業自得だ、ルエリシアはこの比ではないほどに傷ついたはずだ、と思い直して顔を上げる。
「……。怒ってなんて、いないよ?」
だが、彼女はベッドサイドの椅子にちょこんと腰かけたまま、穏やかにそれだけ答える。
――いつかもこうして、酷い怪我をして何日もベッドで過ごす羽目になり、彼女は隣でずっと支えていてくれた。
あの時に約束したのだ。どこにも行かないと。勝手に消えたりしないと。なのに簡単に約束を破った。裏切った。
決して約束を忘れていたわけではなかった。裏切りは自覚していた。
だから、今更こんなことを言い出すのも卑怯だと思う。分かっていてやったくせに。
「……嫌われたく、ないんだ」
ほとんど勝手に、そんな情けない言葉が滑り落ちてしまった。彼女にとっては予想外だったのか、少し驚いたような表情だけが返る。
「酷いことをした。怒っていないと言われてしまっては、どう謝ればいいのか……いや、違う。まだきちんと謝ることすらできていないのにこんな言い方はないよな。……ええと」
馬鹿だ。余計なことばかりを口にしている自覚はあるが、それでも止められず、上手く言葉を作ることもできず。
「……。……怒ってほしい、というのもわがままか。こんなの、自分の罪悪感を消したいだけで……。……本当にどうしようもないな、僕は」
痛い。どこか傷が開いたのではないかと思うほどに痛くて、ほとんど無意識に、ぐっと拳を握りしめる。
「怒られる覚悟でやったつもりだった。……でも、こんなの、覚悟じゃなく甘えだ。怒ってもらえて、それから許してもらえるのが前提の。君が傷付くのを分かっていながらあんなことをして、許してもらえるつもりでいて……。それで嫌われたくない、なんて、僕は……」
ルエリシアは何も言わずにじっとその混乱した言葉を聞いていたが、そこで、握りしめられた彼の手にそっと触れた。
「……大丈夫。嫌いになんて、ならないよ」
彼女はまるで小さな子供をなだめるように優しくそう言って、それから、えへへと苦笑した。
「えっとね。怒ってないっていうのは、ちょっとだけ嘘。ちょっとだけ……まだ許してないから、ちょっとだけ、困らせちゃおうって思ったの。ごめんね」
さらりとそう言ってしまうルエリシア。
何故君が謝るんだ、とか。
そんな可愛い仕返しなんかじゃ帳消しにはならないだろう、とか。
何ひとつ、上手く声にすることができなくて。
「嫌いになんてならない。……大好きだから、朝起きたときにいなくなってたことが怖かったの。大好きだから、無茶をしたことをまだ許してない。……でも、大好きだから、怒りたくないし、許したいの」
一方彼女はひとつひとつの言葉を丁寧に紡ぐ。こんな風に言ってもらえる資格などないように思えて、やはり、何も答えられなかった。
「……それに、エリシャならきっと一人でも行っちゃっただろうから。エリシャと一緒に行ってくれて、エリシャを助けてくれて、ありがと」
そりゃあ二人で行くんじゃなくて先に教えて欲しかったけど、とまるで軽い冗談のように口を尖らせてから、またにこりと笑った。
「……本当に、すまなかった」
ジムノはなんとかそれだけを告げてから、しかし、取って付けたような謝罪だ、と内心自分を詰る。いや、そもそもどんな言葉を尽くしたところで謝罪になどならないように思う。当然悪かったとは思っているが、もし次に全く同じ状況が訪れたとして、それでも同じことをするような気もしているのだから。
「いや……ええと。違う。こんな薄っぺらい言葉で許してもらえるようなことじゃないのは分かっていて……」
視界がぐるぐると回るように感じて、また視線を落とす。
ぐっと握り締めた拳をルエリシアの指先がゆるゆると優しく撫でてくれていて、情けなくなって、また、それ以上の言葉が出なくなる。自分を責め続けていたって、ただ謝ったって、それで彼女が満足するわけではないことは分かっているのだ。彼女は許したいとも思ってくれていて、それに応えたくて。だが、その方法が分からない。
「……ねえ、ジムノくん。……わたしのお願いをひとつ、聞いてくれる?」
「――!」
聞き覚えのある言葉に、彼はぱっと顔を上げる。目が合った彼女は優しく微笑んでいた。
ムラクモとして初めてドラゴンと戦ったとき、ルエリシアに命懸けで庇われたことを彼が負い目に思っていると、彼女はその時もそう問うたのだ。
「ああ。何でも言ってくれ」
あの時彼女は、死ぬな、と言った。
その、いつかは必ず破れる約束を支えにここまで来た。
だから今回も、何だって聞く。どんな願いであっても、必ず。だから――
――明日、一緒に過ごしてほしい。
ルエリシアの”お願い”はそれだけだった。
改めてお願いされるまでもなく、真竜の撃退以降、毎日ほとんどの時間を一緒に過ごしている。ただ単に、13班はまとめて医務区の一室に入院となった上に、退院した彼女はその後も日中はずっと皆を心配して通ってきてくれている、というだけの話ではあるが。いずれにせよ、あえてお願いなどしなくとも彼女がそう望むのなら、いつも通り来てさえくれれば一緒に過ごすことになるのだ。
だから、ジムノは咄嗟に「そんなことでいいのか」と言いかけて、しかし、すんでのところで彼女の真意を察し飲み込んだ。
――彼女が眠っている間に姿を消したのは自分だった。それも、二度も。
来るはずの明日を迎えられなかった絶望。手の届かないところで取り零しそうになる絶望。
考えてみればそんな思いをさせてばかりだった。そんな自分がその気持ちを理解できるなどと言う資格があるとは思っていないが、彼女のその小さな”お願い”に計り知れないほどの重みがあることは察せられた。だから。
「……」
ジムノは13班の居室の前に立ち、しばしドアを見つめたのちにひとつ深呼吸をする。
ここに入るのも随分と久し振りに感じる。戦いが終わってからずっと医務区にいたということもあるが、ミヅチの引き起こした失踪事件以降、空になってしまった10班の部屋を貰い受け、男性陣はそちらに移っていたのだ。
彼はノックもせず静かにドアを押し開ける。松葉杖一本に頼りながらなんとか部屋に滑り込み、そっとドアを閉めた。
まだ早朝で、薄明るい部屋には静かな寝息だけがひとつ。
一番手前のベッドで、ルエリシアが少し身を縮めるように丸くなって眠っているのが見えた。本来同室のサクラはまだ医務区にいて、一人きりであることに油断しているのか、ゆるい寝間着も脱ぎっぱなしの靴もなんとなくだらしない。
ゆっくり近付いて覗き込んでみると寝顔はどことなく険しく、小さな手も布団の端をぎゅっと掴んでいて、あまりしっかりと眠れているようには見えなかった。頭を撫でようと手を伸ばして、しかし結局途中で止めて引っ込める。ずり落ちそうな布団だけ掛け直してやった。
彼は身体を引きずりソファまで引き返し、なんとか身を沈める。久し振りに着た詰襟は、動く度にギプスに引っ掛かり少しきつい。
――彼女が本当に願っていることは、理解している。安心して眠れるような、来るはずの明日を当たり前に待てるような、そんな日々。一緒に生きていきたいという、ただそれだけの望みを失うことに怯えずに済む日々。
そう、それは理解していた。理解していて、それを叶えたかった。そのために戦っていたのだ。だが、ドラゴンさえ駆逐すればよいなどと安易に考えていたのだと、今更自覚させられたように思う。裏切りだと分かってはいて、しかし、叱られて済むとも思っていた。彼女が傷つくことだって理解していたようでいて、理解できていなかった。
だから――今やれることは、やらなければならないことは、彼女の望む明日をひとつひとつ、確かなものにすることだけだ。
「……んう」
ふと聞こえた小さな呻き声に、ジムノは顔を上げベッドの方を振り向いた。丸まった掛け布団がもぞりと少しだけ動き、また止まる。そのまま見つめていると、不意に布団から細い腕の片方だけが生えてきて、伸びをしようとしたのを途中でやめたような形でぐったりと転がった。
ルエリシアの寝起きは悪い。このまま放っておくと、完全に目が覚めるまで更に数時間かかってもおかしくはない。
寝かせておくべきかどうかをしばらく迷ったのち、ジムノは松葉杖に頼りつつ立ち上がった。近付いてみても彼女は全く反応を見せなかったが、空いた左手でそっと頬に触れてみると、「ん」とまた小さく呻く。
少し冷えた柔らかい頬を指先で暖めるように撫でさすってやるとその顔は少しずつ緩み、ふあ、と小さな欠伸を漏らしてから、ようやく目を薄く開いた。
「おはよう」
しっかり目を合わせてそう言うと、
「ん……おはよ」
と、ふわふわと寝惚けた可愛い声が返ってくる。布団に隠れたままだった方の手がもぞもぞと這い出てきて、彼の手に重なった。指が絡まり、にへ、と彼女の表情が緩む。
その油断しきった様子がたまらなく愛おしい。
「もう少し眠るか?」
「……んー……うう、ん……。……。……あ、れ?」
ルエリシアはむにゃむにゃと欠伸混じりの何ともつかない声とともに、今度はしっかりと重たそうな瞼を上げた。重なりあった手の感触を確かめるように握り直す。
「なんでここに……ふあう……」
彼女は眠そうな声のまま、それでも意識はだんだんとはっきりしてきたのか、ゆるりと両手をジムノの顔の方へと上げる。彼がそれに釣られるように少しだけ上体を傾け寄せると、細い指先が彼の両肩に触れた。
何故ここにいるのか。問われたそれを彼も自問する。
今日は一緒に過ごすと約束したから、ではない。それは、彼女が朝に弱いことを知りながらも早朝から黙ってここにいる理由にはならない。
「……早く会いたかったから、かな」
そう答えてみると、ルエリシアはほんの少しだけ驚いたような目で彼の顔をじっと見上げて、それから、ふふっと小さく笑った。ゆっくりと身体を起こしながら彼の首に両腕をするりと巻き付ける。心地好い重み。
「えへへ。わたしも会いたかった」
昨日だって夜まで一緒だったというのにこんなことを言い合っているのがなんだかおかしくて、彼も喉の奥だけで小さく笑った。片腕で彼女の背をぎゅっと抱き締めると、柔らかい感触がじんと心臓まで沁みる。
「……でも、まだケガが治ってないんだからダメだよ? 医務区で待っててくれてよかったのに」
「もう平気だ。ほとんど治ってる」
「さすがに松葉杖ついてるのを治ってるとは言わないよ」
優しく咎めるような響きも耳にくすぐったくて、心地好くて。ずっとこうしていたいと思えるような温かさが腕の中を満たしていて。
「……わたしの力が戻ったら、すぐに治してあげられるのにな」
しかし、そんな少し悔しそうな口振りが、多幸感にちくりと刺さる。
真竜との戦い以降、ルエリシアはサイキックをほぼ失ってしまっていた。キリノ曰く”エネルギーを保持するタンクが壊れたような状態”だそうだが、それさえも――
「僕たちのせいだ。あんなことをしていなければ、君にそこまで無理をさせることもっ、……」
謝ろうとしたその言葉は、ぺとりと唇に置かれた細い指先ひとつに遮られた。
ミヅチに二人で挑んで死にかけて、その傷も癒しきれないままに真竜に挑んでまた死にかけて。ルエリシアには必要以上に治療の負担を掛けてしまった挙句、最終的には、たった一人で真竜と対峙させる羽目になってしまったのだ。サイキックが彼女の身体に大きな負担をかけることなど、出会った時から知っていたというのに。
彼女はそっと指を離すと、少し困ったような顔をわずかに背けた。
「……ううん、ごめん。えっと、今日はそんな話をしたいんじゃなくて……」
「……ああ、そうだな。……ラウンジで朝食でも食べようか」
努めて柔らかい口調でそう提案すると、ルエリシアは一転きらりと艶やかな目を上げて、嬉しそうに緩めた。
「――うん!」
フロワロの散り消えた東京が、今日も変わらず静かに眼下の世界を埋め尽くす。
ドラゴンが消えたところで死んだ人間が戻るわけではない。マモノが住み着きインフラも止まった街ですぐに生活できるほど強くもない。そもそも、ほんのわずかに生き残った人間が必要としている土地もまたわずかばかりで、そこを維持するのが精一杯であり充分でもあり、つまりは、この灰色の景色が動くことは当分ないのだろう。結局人間はこのまま滅びゆくのかもしれない。
それでも、
「わあっ、今日はいい天気だねえ」
ルエリシアは、その景色にそう声を弾ませた。窓の外に気を取られてか、両手に抱えた大きなトレーがやや傾いているので、その上に乗ったコーヒーとサンドイッチが惨事になる前にジムノは片手でそれを引き受けてローテーブルへと置いた。
ラウンジの個室は相も変わらず趣味の悪い桃色のコーディネートだ。窓の外に広がる殺風景な灰色とのコントラストに酔いそうだ、と彼は内心で思いつつも、ルエリシアがここを気に入っているようなので何も言わない。確実に二人きりで落ち着いて過ごせる数少ない空間なので、まあ、内装など何でも構わないといえばそうなのだが。
確かに灰色の街の上には秋晴れに澄んだ青く高い空が広がっていて、これなら屋上で過ごすのも良かったかもしれない。いや、まだ少し暑いだろうか?
松葉杖を適当なところに立て掛けてから柔らかすぎるソファにゆっくり身を沈めると、ルエリシアもぱたぱたと駆け寄ってきて隣に飛び込んできた。
「えへへ。じゃあ、食べよっか」
にっこりと見上げてくる笑顔が朝日に眩しい。
「そうだな」
「いただきまーす」
ルエリシアはサンドイッチに手を伸ばし、小さな口いっぱいにかぶりついた。
「んーっ、おいひい」
エリシャがこの場にいたら行儀が悪いと顔をしかめるところだろう。もはや何に急かされるような世界でもないのだからもう少し落ち着いて食べればいいものを、あっという間に二口目。
幸せそうに食べる様子を横目に、ジムノもまたサンドイッチを手に取る。保存食のパンをスライスして豆乳で作ったクリームと缶詰のフルーツを挟んだもの、らしい。
まだ厳しい戦いが終わったばかりで、新鮮な食糧など当分は手に入りそうにもないこの状況下。工夫を尽くして非常時らしからぬ食事を提供するこのラウンジは人気のスポットになっていると聞いていた。彼は食事の質にあまり興味がないし彼女もまた何を食べてもおいしいと言うが、その彼女がいつもよりも更に嬉しそうに頬張っているのだし、時々訪れるのもいいかもしれない。
そんなことを考えながらジムノも一口かじってみると、想像よりも優しい甘さが広がった。
上機嫌のルエリシアはあっという間に一切れを食べ終わり、すぐにもう一切れに手を伸ばす。元々二切れ乗っていた皿はつまり空になり、ジムノは何も言わずに一切れ乗った自分の皿と入れ換えた。
「? 口に合わなかった?」
「いや。だが、自分で食べるよりも、君が美味しそうに食べているのを見ている方がいい」
「ええっ?」
ルエリシアはやや困惑した様子を見せつつも、じゃあありがとう、とはにかんだ。
「……ふふ。でも、良かった」
ぺろりと二切れ目も腹に収めた彼女は最後の一つを大事そうに両手に取る。
「……?」
ジムノがサンドイッチを咀嚼しながら疑問を含めた視線だけを向けると、彼女は一瞬だけ迷いのような間を置いてから、
「戦いが終わってから……今日、初めてちゃんと笑ってくれた気がする」
と、少し遠慮がちに呟いた。そんなことを全く自覚していなかった彼がほとんど反射的に表情を引き締めてしまうと、彼女はくすくすと笑う。それに彼はきまり悪く手元に視線を落とした。
「……そう、かもしれないな。……やっと実感できたんだ。あれほど赤かった景色からは花弁の一枚に至るまで消えていて、ドラゴンだってどこにも飛んでいなくて……」
どこかぼんやりとした言葉に、ルエリシアは「そうだね」と優しく応える。再び顔を上げると、彼女は笑ってまたサンドイッチをかじった。
「……ねえ。前にさ、わたしがジムノくんの生きる理由を作った、って言ってくれたでしょう。その理由は、まだ、ある?」
確かにそんな話をしたことを思い出す。
戦いの中でいっそ命を落とすことを望んでいるのだという同じ秘密を共有して、しかし、そうしているうちに生きたいと思い始めたこと。生きる理由はルエリシアが作ってくれたこと。そして、彼女も同じように彼のおかげで生きたいと思うようになったようになったのだということ。
あの時は互いにその理由を明かすことはなかった。口にする勇気がなかった。
ルエリシアは微笑んだまま――しかしどこか不安そうにも見える。サンドイッチの一口分だけを手に残し、僅かに震える睫毛の上目遣い。
「ああ」
今なら言える。――否、今言わなければならない。きっと今日はこのためにここに来たのだ。そう思えた。
「……いつか、君には報われてほしい、と言ったが。それだけじゃ足りない。幸せでいてほしい。僕は……そのための力になりたい」
震えそうになる声をなんとか抑えてそう告げる。ひどく傷つけておいてどうしてこんなことが言えようか、とも思ったが、ここで逃げるのは、きっと、もっと苦しい。
ルエリシアは驚いたように目を丸くしてから、ふわりと表情を綻ばせた。
「……わたしも。わたしも同じだよ。ジムノくんがいつか、そうやって表情を隠さなくてもいいようになってほしい。幸せでいてほしい。……そのための、力になりたい」
心臓の底がぐらりと急激な熱を持ったように感じ、彼は咄嗟に視線をどこへともなくずらす。何と応えるべきかもわからず、ただ「そうか」とだけ呟いた。その様子にルエリシアがくすくすと笑うので、余計に目が泳ぐ。
サンドイッチの最後の一口を飲み込んだ彼女は満足そうに彼へと体重を預ける。その重みと体温がじんわりと愛おしくて、彼もまたサンドイッチをすべて飲み込んでから、そっとその肩を抱き寄せた。それに応えるようにぎゅうっとしがみついてくる彼女は嬉しそうに「ふふっ」と笑う。
「……ずっと、そばにいてね」
囁くような声音がくすぐったい。幸せそうでいて、しかしどこか不安定な、掴まるところを探して空を掻く指先のような、そんな歪みが胃の表面を掠める。
「ああ、約束する」
だから彼は咄嗟にそう答えて、それから細い身体を両腕でしっかりと抱き締め返した。「うん」と小さな声が胸のあたりに直接響く。
「……いや。約束を破ってばかりの僕が言ったところで説得力はないな。……信じてほしいとか許してほしいなどと言うつもりはない。だが――」
なんだか耐えられなくなって、あまりに言い訳がましい口調を自覚しながらもついそんなことを口にしてしまい、しかしそれはルエリシアのおかしそうな笑い声に遮られた。
「もう。……信じてる。それに……、……許すよ。ごめんね、意地悪して」
彼女は大人だ、とジムノは思う。
本当はまだ割り切れてなどいないくせに、そんなことを言って自分の内だけで折り合いをつけようとして。
もっと我儘を言ってくれていいのに、何だって聞くつもりがあるのに。
だが同時に、どんな我儘を叶えたところで、彼女の傷がなかったことになるわけではないことも理解している。
「だから、このことはこれで終わり。ね?」
だから、顔を上げてそうにこりと笑うルエリシアの、強がりで踏み出した一歩をせめて無駄にしないために、
「……わかった。ありがとう」
ただそれだけ答える。彼女が黙って飲み込むのなら、自分も黙って応えるまでだ。
彼はそう決意し、小さな身体をもう一度抱き締め直した。