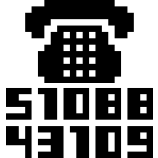日は傾きつつあり、普段なら点く街灯もビルの明かりもない。
「夜って……どうするのが一番安全なんだろう?」
薄暗くなってきたコンビニの店内。すっかりぬるくなってしまったであろうケーキのパッケージを開けながら、ルエリシアは呟いた。
「外が見えるところにいる方が安心する気がするんだけど、外からも見えるってことでもあるし……やっぱり眠るなら隠れていた方がいいのかなあ?」
フォークあるかな、と膝に掛けていたブランケットからごそごそと抜け出し、レジカウンターの中を漁る。
「好きなところで休むといい。その間は僕が見張りをする」
ジムノはそう答えた。
「ええっ!? それはさすがに悪いよ」
ルエリシアはそう声を上げながらプラスチックのフォークを二つ握って戻ってきて、片方を彼に差し出してくる。
「はい。一緒に食べよ。……夜はちゃんと寝ておかないと。疲れも取れないし」
彼はあまり食欲がないままだったが、それを素直に受け取り、ビニールの袋を裂いた。
「二人とも眠っているところを襲われる方が困るだろう? 前後に仮眠を取れればそれで構わないし、その間は君が起きていてくれるならお互い様だ」
「うーん……分かった。じゃあ、明日は交代しようね」
「……まあ、それは明日考えよう」
プラスチックのトレーにはイチゴショートとチョコレートが一つずつ乗っていて、ルエリシアはイチゴショートにフォークを沈めた。
「だめだよ。いつまで続くかも分からないんだから、無理はしないで。明日は交代、ね?」
ジムノはチョコレートケーキを一口分切り取って口に運ぶ。
夜更かしを咎めるような口調がその小さな身体から出てくるのがなんだかおかしくて、少しだけ笑いそうになるのを甘さでごまかした。
「それ、おいしい?」
「うん?……まあ」
「ちょっとだけちょうだい」
彼女は答えも待たず、小さく切り出したチョコレートケーキを躊躇なく頬張った。
ジムノは一瞬だけそれにぎょっとする。
憂鬱な昼休み、クラスメートが毎日飽きもせず弁当をつつき合っている様子が視界をちらつくのが嫌いだったことを思い出して。
「……」
思いもよらず自分がそんな風景の一部になったことに、心臓を掴まれたような気分になったのだ。
幸せそうに表情を緩ませるルエリシアをつい凝視してしまい、それに気付いた彼女は「しまった」とばかりに慌ててその顔を引き締めた。
「あっ……ご、ごめんねっ!? 行儀悪いからやめなさいっていつも言われるのに、その、おいしそうだったから、つい……」
慌てて言い繕うその様子とあまりにも素直な言い分に、彼は結局笑ってしまった。声を殺して、肩を震わせて。
ほんの些細なことで笑っている自分がまるで別人のように思えて、余計におかしくなってくる。
心から楽しい気分で何も気負わず笑っているなんて、いつぶりだろうか。
「えっ……? えっ?」
ルエリシアはそんなジムノの反応が予想外だったらしく、戸惑いと驚きが混じったような声を上げる。
ころころと変わる表情は眺めていて飽きない。
彼は、なんでもない、とかぶりを振った。
「美味かったか?」
「うん!」
彼女はまた顔を緩ませて即答した。
「じゃあ、残りも食べて構わないぞ」
ジムノは自分の顔まで更に緩みそうになるのを自覚しながらそう伝え、さっさと自分のフォークをゴミ袋に投げ込む。
自分で食べるより、彼女が食べている様子を見ていたい、と思った。
「ええっ!? で、でも……」
「サイキックを使うのに必要なんだろう?」
遠慮を見せるルエリシアにそう理由をつけてやると、彼女は一瞬きょとんとして、それから笑った。
「あー……えへへ。うん、じゃあ……ありがと。でも、一口だけ、交換ね?」
ルエリシアはフォークにショートケーキの一口分を乗せるとジムノの口元へと突き出してくる。
「……」
知り合ったばかりの少女が自分の使っていたフォークで差し出してくるものをそのまま食べるのは……色々と、どうなのだろう。気にしすぎなのだろうか。彼女が気にしなさすぎるのだろうか。しかしいずれにしろ、断って引っ込めさせるのもなんだかおかしな気がする。
目の前のケーキにじっと視線を置いたまま固まっていると、彼女はさすがに怪訝そうな顔で首を傾げた。
「生クリームは嫌いだった?」
「い、いや……そういうわけではなく……」
覚悟を決めてそのケーキを頬張る。彼の口からフォークを抜いて、ルエリシアはにっこりと笑った。甘い。
「おいしい?」
「……まあ」
小さく頷くと、彼女は満足気にまた自分の口へとケーキを運ぶ。
調子が狂う、とジムノはこっそり嘆息した。
決して不快というわけではないのだが、人付き合いが皆無だった彼には距離感の掴み方が分からない。
友人がいれば、こういう感じだったのだろうか。……本当に?
そんなことを思いながら、その場に横になって目を閉じてみる。
今日はひどく疲れた。
店の奥や商品棚からかき集めた布切れを敷いてみただけの寝床はお世辞にも寝心地が良いとは言えないが、この疲れなら問題なく眠れそうな気がする。
「……明日は、替えの服とか、お布団になりそうなもの探してこなきゃね」
ルエリシアはケーキを平らげて、そう呟いた。
「そうだな。あとはドラッグストアにでも行けば、当面必要なものは揃うだろう」
ジムノが答えると、少しの間を置いてから、ルエリシアは小さく声を上げて楽しそうに笑った。
「? どうした?」
「明日どこに行こっか、なんて。こんなめちゃくちゃな状況になって初めて……普通の高校生みたいなお話をしてるのが、なんだかおかしくって」
言われてみれば、と彼も思った。
他愛のない会話をしながら食べ物を分け合って、明日の予定を相談して。
そんな記憶はひとつもなかった。
「……はは。そうだな、今更、普通の……」
彼女の言葉を繰り返そうとして、言葉を止めた。
目を開けて身体を起こす。
「……。……高校生?」
新たな食べ物を物色しているルエリシアに視線を投げた。
言動は妙にしっかりしているものの――幼さの残る顔立ち、彼よりも頭二つ以上低い身長、そしてその身長を考えても細い身体。その身体を包むひらひらとした服装。彼はいくつか年下だとばかり勝手に思っていたのだが――
「……君、いくつなんだ?」
「? 十七歳だよ?」
「……」
「え? 何? どうしたの?」
思わず額を押さえる彼に、ルエリシアはいくつか疑問符を浮かべて首を傾げる。
「いや……。……その……すまない。同い年だとは思っていなかった」
「ええっ!?……そ、そっか……」
自分の容姿に自覚がないのか、彼女は服の裾をつまんでみたり、什器の金属に自分の顔を映してみたりする。
その姿がなんだか小動物のようで可愛らしい、とジムノは頭の隅で思ったが、言葉にすると更にがっかりされるような気がしたので黙っておくことにした。
――彼女は何者なのだろう、とぼんやり思う。西洋系の幼い容姿。姿どころか実年齢にもそぐわない冷静さと判断力。サイキック。謎の男たちに追われていたこと。彼女の言い様からすると普段は普通の高校生をしているというわけではないのだろうし、全く想像が付かなかった。
「……答えたくなければ答えなくていいんだが」
ジムノはそう切り出す。
さっさと仮眠を取ろうかとも考えていたのだが、すっかり眠気が飛んでしまった。
「昨日は、何故追われていたんだ? あいつらは何者だ?」
その問いに、ルエリシアはあどけない顔を上げる。
「家出したわたしを連れ戻すために追いかけてきてた人たち、だよ」
聞かれたくない話というわけではないのか、サイキックの話を打ち明けた時に比べると随分あっさりと口を開く。それは極めて端的な答えだが、かえって謎が増えた。
「……家出?」
「うん。いろいろあって、一年くらい前に家出して、東京に来たんだ」
分かりやすい言葉だが、やはり分からない。
「……。一年間、家出生活していたのか? 一人で?」
大人ならともかく、十六歳だか十七歳だかで乗り切るには厳しいだろう、と思う。仮に追われずとも、生きていくだけで充分苦労しそうだ。
どこでどう過ごせばいいのか想像も付かない。
「ううん、一人じゃないよ。兄弟と一緒に」
彼女はにこやかにそう語る。
「といっても血は繋がってないし年は同じなんだけど、一緒に育った……お兄ちゃんみたいな人」
「さっき話していた『連れ』か」
「そう。ずっと二人で逃げてたんだ」
「……あの男たちは? 家出した子供二人を探すにしては随分物騒な奴らに見えたが」
「お母さんが雇った人たちみたい。よく知らないけど」
「……そうか」
苦労したんだな、と言おうとして、その一言が喉に詰まる。彼女が経験してきたことはあまりにも想像を絶していて、そんな言葉では軽すぎるような気がする。
とはいえ適切な言葉が見つかるわけでもなく、ジムノは黙り込んだ。
そんな彼の反応に、ルエリシアはきょとんとした顔で首を傾げる。
「家出の理由は訊かないんだ?」
「……話したくはないだろう?」
理解を超えた世界だが、相当に複雑な家庭環境であったことだけは分かる。
家出した子供を連れ戻すために怪しげな人間を雇う母親。ただ心配して形振り構わないだけ、とは思いがたい。どういうわけか知らないが、警察に届けてすらいない可能性が高いからだ。――ルエリシアたちにもまた、そういった公的機関に頼れない理由があるのだろうが。
そして、そんな追手を長期間雇えるのだから、相当裕福な家であるはずだ。だが、たとえ家がどれだけ裕福であっても――もしくは裕福であるからこそかもしれないが、それを補って余りある苦しみがあったのだろう。そうでもなければ、子供だけで一年間も逃げ続けるほどの気力を保てるとは思えない。
「うーん……まあ、確かに楽しい話じゃないけどね」
彼女は苦笑し、独り言のようにそう呟いた。先程の話しぶりからすると、ずっと長い間、普通ではない生活を強いられてきたのではないだろうか。
それでも彼女は優しく笑い、自身が傷つくことも厭わず他人を助けるのだ。
ただ他人を遠ざけていただけの自分が、ひどくちっぽけな存在に感じた。
「……君は、強いな」
「そう……かな」
ルエリシアは表情を少しだけ曇らせる。
その理由が彼には分からないが、それでも頷いた。
「ああ」
それから、もう一度敷き詰めた布に身体を横たえる。
「だが今はこんな状況なんだ、無理はするな。……仮眠を取るから、そうだな、二時間くらいしたら起こしてくれるか? それと、何か異変があったときもすぐに起こしてくれ。絶対に、君だけで対処しようとは思うなよ」
彼女は、一緒に生き延びよう、と言ってくれた。
それなら自分も強くならなければと彼は思う。
傷つきながら誰でも助けられるようになれるとは思わないし、なりたいとも思わない。だが、せめて――自分を拒絶しないでいてくれる人くらいは。
ルエリシアはにっこりと笑った。
「うん、ありがと。……おやすみなさい」
「ん……。……おやすみ」
なんだかくすぐったく感じて、彼女に背を向ける格好で丸くなり、目を閉じた。
――夢を見た。
一人で化け物から逃げ続けるだけの夢。何度も脚がもつれ、転び、這うように逃れ、血にまみれ、気が付いた時にはまた走っている。
人間と出会うことは一度もなく、ただ怯えて逃げ続ける悪夢。
「ねえ、大丈夫?」
――
「ねえ……ねえってば」
優しい声に呼ばれて、ジムノは目を開けた。
ルエリシアの心配そうな表情が、薄明かりに浮かんでいる。
「……なんだ?」
ぼんやりと答えて上半身を起こした。妙に冷たい汗がじっとりと染みて気持ち悪い。
「すごく……うなされてたよ」
「……そうか」
彼女は少しだけほっとした様子で、タオルを手渡してくれた。
「……ありがとう」
ルエリシアの存在がありがたかった。
もし彼女に出会えず一人だったとしたら、この夢は現実のものとなっていただろう。
「ん。……もう少し眠る?」
「いいや。やめておこう」
あまり疲れが取れた気はしないが、ここから寝直せるほど太い神経ではないことは自覚している。
外に光を漏れにくくするためか布切れが軽く巻き付けられた懐中電灯が商品棚にくくりつけられているのが目に入り、仮眠を取る前の会話を思い出す。
「……それは、逃亡生活の知恵か?」
問われた彼女は、ジムノの視線の先を追って、苦笑した。
「あー……あはは……まあ、ね。何も見えないと困るけど……夜の光は目立つから」
ジムノは立ち上がると、棚越しに外の様子を覗き見た。
空が見えるほど視界は広くないが、どうやら日が沈んでしばらく経った頃らしい。
「……変わったことはなかったか?」
やはり一帯が停電しているのか、人工的な明かりは全く見当たらない。ただ、月が出ているようで、その景色は少しだけ明るかった。
「うん。たまに外で物音がしたり何か通ったりしてるけど、気づかれてはないみたい」
「そうか。じゃあ、そろそろ君も休むといい」
「まだ眠くないなあ」
「言ってる場合か。眠くなくても横になって目を閉じていろ」
「うーん」
彼女はそう唸りつつも言われた通りにその場で横になろうとして、ジムノはそれに少しだけ慌てる。
「……いや。待て。奥で休んでいいんだぞ」
「ここがいい」
彼女はそう即答し、ブランケットにくるまった。
「……いくらなんでも無防備すぎないか?」
「棚の陰だから外からはほとんど見えないし、大丈夫だよ」
そういうことではなく、と返そうとして、やめる。
こんな時に変な気を起こすつもりは毛頭ないし、警戒されたいわけでもないのだが、複雑な気分だ。
「そういえば、エリシャにもよく無防備って言われたなあ」
彼女は思い出したようにぽつりと呟いた。
「……あ。エリシャっていうのは一緒に逃げてた人ね」
兄のような存在だという連れのことか。
一緒に育った相手にまで言われるというのはかなり重症のような気がするが、何も言わないでおく。
「無事でいるかな……」
不安そうにほんの小さく呟いてから、彼女は苦笑した。
「……あー……ううん。やっぱり夜は怖くなっちゃってダメだね。ねえ、眠くなるまでお喋りに付き合ってもらっても……いい?」
「ああ」
ジムノが短く了承すると、ルエリシアの表情は少し緩む。
「よかった。……あのさ、この間電車に乗ってたときにね――」
それから彼女が寝付くまで、とりとめもない話は続いた。
ジムノは目的のない雑談は不得意だったが、ころころと流れて跳ねて転がるような彼女の声を聴いているだけでも、なんとなく気分が良かった。教室で耳に入る誰かのくだらない会話は不快だったのに。
彼自身が嫌になるほどの愛想のない下手な相槌に気を悪くすることもなく、楽しそうに、嬉しそうに、ルエリシアは話す。
街で見かけた野良猫の話。駅で迷っていたはずが何故か気付くと隣駅にいた話。東京から見える星は随分少ないという話。
彼なら見過ごすようなほんのちょっとした驚きや感動を、目を輝かせて言葉にする彼女が、眩しく見えた。
――ここまで長く感じる夜は初めてだった。
月までもが沈んでしまい、外はすっかり闇に包まれ、光を抑えた懐中電灯だけが頼りだ。
ただ暗いだけではない。外を通る人や車がいるわけもなく、電気の通らない照明や冷蔵庫は微かな唸りすら上げない。電池式らしい壁掛け時計の秒針の音や外の風の音、そして隣で眠る少女の呼吸がやけに目立って聞こえる。
静かなだけならいい。彼女の言っていた通り、近くを化け物が通り過ぎていることがあるらしく、たまに耳慣れない物音がするたびに緊張が走る。
うっかり眠らずにいられるだろうか、と考えていたが――とてもではないが、眠りたくても眠れなさそうだった。
疲れているのは確かだが、物音に、影の微かな動きに、感覚を澄ませていないと落ち着かない。
ルエリシアが眠ったら商品棚に並んでいるであろう適当なシャツに着替えてしまいたいと思っていたのだが、ビニール袋でがさごそと音を立てる気にはなれず、せめて明るくなってからにしようと思い直した。汗はとっくに乾いてしまったが少し気持ち悪い。
何時間もほとんど身動きをせず気を張ったままでいるのは酷く疲れる。
途中、雑誌の棚から一冊手に取ってみたが、全く内容が頭に入らず、かえって焦燥感や恐怖感を煽るだけの結果になってしまった。
これで何度目か、腕時計にちらりと視線を落とす。日が昇るまではあと二時間程度といったところだろうか。
ルエリシアの言う通り、こんな夜を毎日過ごすのは確かに無理がありそうだ。睡眠時間はともかくとして、この緊張感にはどこかで参ってしまうだろう。
彼女はこんな夜を迎えたことがあるのだろうか? こうしてどこかに身を隠して、いつどこから追手が来るかに怯えながら、眠ることもできず。そして、そこまでしてでも家を出る理由が、戻りたくない理由があって――
「……?」
――そんなことを取り留めもなく考えていると、そのうち、異変に気が付いた。
微かに、地響きのような音がどこかから聞こえているのだ。かなり遠いのか、それとも単に大きな音ではないのか、いつから鳴っていたのかも分からないほどだが――妙に不安を煽る音だ。距離も方角も分からない。
それ以外の違和感はなく、どうすべきなのか判断がつかない。
ひとまず眠っているルエリシアのすぐ傍まで寄り、何があっても対応できるよう身構える。
数分はそのままでいただろうか。
音はほんの少しずつ大きくなっているようにも聞こえ、そのうち、ついに床が微かに振動し始めた。
ただの地震かとも思ったが、それにしては長すぎる。
「……何が起こっている?」
既に今、突然化け物が現れ、東京が――あるいは世界が滅びかけている、という前代未聞の状況なのだ。
他にも想像すらできないような何かが起こったところで不思議ではない。
みし、とどこかが軋む音。あまり遠くない。
「ルエリシア」
少女を揺り起こす。彼女は少しの間むにゃむにゃと寝ぼけていたが、異常が起こっていることに気付いたのか、ゆっくり身体を起こした。
「あれ……? 何、この音……?」
「分からない。だが、無視できるものではないようだ」
軋むような音に加え、そのうち、どこか遠くから何かが壊れ崩れるような音も聞こえてきた。
不穏な空気だけが流れるが、何が起こっているのかはさっぱり分からない。
「どこかで、建物が壊されてる……とか?」
「確かにそういう感じには聞こえるが……」
そんな会話を交わす間に、様々な音は急激に大きくなり始めた。
明確な地響き、建物が軋む音、破壊される音。
床も振動しているままだが、大きな地震のように揺れているわけではない。
外に逃げるべきか留まるべきか、と迷うが、外の暗闇のことを考えると留まる方がいいように思えた。
「わっ……!?」
ルエリシアの身体を引き寄せてその頭を胸のあたりに抱え込み、彼女の使っていたブランケットを一緒に被る。
仮にここが全壊するようなことがあれば無駄な抵抗かもしれないが、そうでないなら、傷を治す能力を持つ彼女の安全が最優先だ。
「悪いが少し我慢していてくれ」
その言葉が届いたかどうかも分からないくらいの轟音が重なる。近くでどこかの建物が崩れたらしい。
彼女は震える手でぎゅっとしがみついてくる。
暗闇に響く音にじっと耐えているうちに、やがて音は小さくなり、そして再び静寂が戻ってきた。
だからといって危機が去ったと判断していいのかどうかは分からないが、ひとまず警戒を緩め、彼女の身体を放してやる。
「ありがとう……大丈夫だった?」
「ああ」
周囲の様子を確認しながら頷く。
相変わらず懐中電灯の光が届く範囲しか見えないが、店内に異常はなさそうだった。
「どうやら運が良かったようだな」
「何が……起こったんだろ?」
「朝になったら確認しよう」
明らかな異変を把握しないままでいるのはどうかとも思うが、だからといってこの暗闇では何も見えないし、懐中電灯を持って出るのも自殺行為だろう。
「……うん」
それまではここで警戒しているしかない。真剣な顔で頷いたルエリシアは、ぎゅっとブランケットの端を握りしめている。
「もう少し眠っておくか?」
問うと、彼女はかぶりを振る。
「……ううん、わたしはもう充分寝られたから大丈夫。……交代する?」
「いや。何があったのか把握するまでは落ち着かない」
「それもそうだよね」
結局、二人して隅に身を寄せ合って座り、また些細な話をしながら明るくなるのを待ったのだった。
「……これは……」
ジムノは絶句した。
空が白み始めたのでまずは外の様子を伺おうと立ち上がってみると、そこには全く予想外の光景があった。
やや呆然としたまま、不用心にガラスの壁まで歩み寄る。
外はビルばかりだったはずが、何故か多くの樹木が生い茂り、森のようになっているのだ。
「ど……どういうこと……?」
ルエリシアも隣で同じように呆然と呟く。
まるで意味が分からない。
いよいよ自分の頭がおかしくなってきたのかとも思ったが、ルエリシアの困惑した反応を見る限りは残念ながらそういうわけでもないらしい。
「……外を見てくる」
ジムノはそう告げて、注意を払いながら扉を少しずらした。
「待って、わたしも行く」
彼女は慌ててついて来る。
二人で外に出て扉を閉め直し、改めて辺りを見回す。
むせかえるような植物のにおいが辺りに充満していた。
「本物の木……みたいだね」
ルエリシアは一番近くにあった木の幹に恐る恐るといった様子で触れる。
アスファルトを割って生えてきた木々は、道路の真ん中に、歩道に、あるいはビルを突き破るようにして立ち並んでいる。
まるで何十年も経った廃墟の街のようだ、とジムノは思った。
「……そうだな」
風が吹くとざわつく葉の音がなんとも穏やかで、緊張感を忘れそうになる。
「一晩で……っていうか、あの何分かでこんなことに……?」
「……少し、周辺を見てみよう」
この現象はどのくらいの範囲で起きているのか。他に変化はないか。知るべきことはいくらでもあった。
「うん。できれば、昨日言ってた物資の調達もしよっか」
困惑しつつも冷静にそう言って、彼女は頷いた。
道玄坂を下り渋谷駅方面へと向かっているうちに、今更のようにもう一つの大きな変化に気が付いた。
「……どうかしたの?」
周囲を見回すジムノに、ルエリシアは首を傾げる。
「人間の死体が……消えてる」
「あっ……そういえば、確かに」
彼女もはっとしてぐるりと視線を動かす。
至る所に折り重なるようにして死んでいた人間が忽然と姿を消しているのだ。
まるで何事もなかったかのように、人間が消えて木々が生い茂り赤い花が咲き誇る渋谷の景色が、気味が悪いほど穏やかに広がっている。
「な、なんで……?」
仮にどこかからの助けが来るとしても、死体の片付けだけがそんなに早く済むはずがない。
化け物が人間を捕食でもしているのかとも思ったが、昨日の今日で血の一滴も残っていないということがあるだろうか。
グロテスクな光景を見ずに済むのは助かるが、決して喜ばしい状況ではなさそうだ。
ルエリシアは息を呑むと、ジムノの腕につかまってきた。その顔色はあまり良いとは言えず、彼女もまたこれを不穏に感じているのだろう。
「……」
小さな唇をきゅっと引き結び、不安そうな顔で見上げてくる。
何か言葉をかけてやるべきかもしれないが何も思いつかず、少しゆっくりと歩みを進める。
「……もしかして、ここで死んだら……何も残らず消えちゃうのかな」
彼女は俯いて、ぽつりと呟いた。
「死んだ後に消えるくらい構わないし、そもそも死んだらそれっきりだ。その後のことなど考えても仕方がない」
ジムノは淡々と答える。
それに――もし消えるのならそれもいい、と彼は思った。
ただ身体が消えるくらいでは足りないくらいだ。
消えたいと思ったことなど、今までに何度もあったのだから。
自分が消えたところで世界は何も変わらず進むのだし、最初から存在しなかったことにできれば、痕跡も残さず誰の記憶からも消えることができれば――と。
自分が消えて悲しむ人がいるとすれば兄姉くらいだろうし、その兄姉に対してすら、本当は自分のことなど疎ましく思っているのではないかという疑心暗鬼に陥ることもあるほどだったのだから。
「……そう……かもしれないけど……」
悲しそうな表情を浮かべる彼女から思わず目を逸らした。
「……でも、わたしは……ジムノくんには消えてほしくないよ」
予想もしていなかった言葉に、ぐっと息が詰まったような感覚を覚える。
――嫌っていた有象無象の他人が丸ごと消えて、突然現れ自分を否定しないでいてくれる少女と二人きり。
常に死と隣り合わせであるという点を除けば、それは今までに何度も望んだことのある状況だということに気付く。
あまりにも都合の良すぎる世界と言っていい。
五感はこれが夢などではないとはっきりと主張しているが――
「……まさか、こっちが死後の世界か何かじゃないだろうな?」
そんなものは信じたこともなかったが、よくよく考えるとその方が自然にすら思える。
「えっ……」
「……いや、なんでもない。そんなことは考えても無駄だな、証明する手立てがあるわけでもないし。それに……」
馬鹿な妄想をしている場合ではない。
「何が起こっているとしても僕たちのやれることは変わらない。消えたくないのならまずは物資を調達して来ないとな」
「ん……そうだね」
ルエリシアは曖昧に笑った。
毎日駅と学校を往復していただけなのだから、渋谷の街には詳しくない。
ただでさえどこに何の店があるのかもよく知らないというのに、突然現れた木々のせいで景色が大きく変わり、まるで初めて訪れたような感覚だ。
「服だけはいろんなところで手に入りそうだね」
ルエリシアは日用品や食料の詰まったビニール袋の持ち手をしっかり握りしめてそう呟く。
「……ああ」
ジムノも同じく袋を手に、辺りをゆっくり見回しながら、半分上の空で頷いた。
「……? どうかしたの?」
きょとんとした声に、どう答えるべきかとしばらく悩んだ後、やはり周囲に視線を配りながら正直に答える。
「どこか……近くに、僕らと同じような生存者がいるんじゃないかと思う。さっきのドラッグストア……水のペットボトルが全部なくなっていた。おそらくあの様子だと、昨晩から今朝にかけて回収していった人間がいるんだろう」
「ほんと!?」
彼女は明るい声を上げる。だがジムノは少し冷たくその顔を見下ろした。
「……念のために言うが。警戒してるんだ」
「警戒って……」
今は見られているような気はしないし、人影も見当たらない。
この状況で水を大量に確保するということは、相手は長期的にこれが続くことを見込んでいるか、それなりの人数がいるか、もしくはその両方だろう。一度に全て持ち去っているのは他の生き残りに奪われないようにするためか。
「……この状況で最も恐ろしいのは……親切を装って近寄ってくる、悪意のある人間だからな」
彼女ははっとしたように息を呑んだ。
助け合うべきだという反論があるかと思ったが、そういうわけでもなく、小さく頷く。
「うん。そう……だよね」
彼女は何か思うところがあるのか、噛み締めるように呟いた。
その真意は計れないが、少し思い詰めたような表情を見ると何故だか苦しく感じる。
「……とにかく、一度拠点に戻ろう」
服の替えを探すには荷物が多すぎる。そう告げて拠点のコンビニの方角へと足を進め――
突然、ぞわり、と背筋に気持ち悪い感覚が走った。
何かの気配、いや殺気と言うべきものだろうか。理屈では割りきれないが、はっきりと感じる。
人間のものとは思えない。
――どこかに、化け物がいる。
「……」
ジムノは黙ったまま、斜め後ろを歩いていたルエリシアを手で制した。
彼女は素直に歩みを止め、しかし化け物の気配に気付いてはいないのか、怪訝な――しかしわずかに緊張した表情で彼を見上げる。
どこだ。
彼は周囲に視線を走らせるが、目立った異変はない。
荷物をそっと下ろして身構える。
言葉を交わすまでもなくルエリシアは状況を察したのか、彼女もまた荷物を下ろし、慎重に周囲を見回し始める。
そのまま数十秒ほどが過ぎ――
「……!」
背後でルエリシアが息を呑む。
どうした、と訊くよりも早く異変が起こった。
真上で、ヴン、と空気が唸るような音。
見上げるよりも早く、爪先の十センチ先、足元のアスファルトが砕ける。
「なっ……!?」
ジムノは慌ててルエリシアの腕を掴み数歩下がる。それと同時に、また空気の唸る音。続いて今度はたった今までルエリシアが立っていた場所が砕け、その衝撃ですぐ側に置かれたビニール袋が弾けた。中身が吹き飛び散乱する。
それからようやく天を仰ぎ見ると、そこにいたのは巨大なトンボだった。
羽音も立てず機敏に飛び回りながらもこちらをじっと見下ろしている。
巨大といっても、昨日見たウサギやカエルとさほど変わらないサイズ。しかし、それらの化け物とは比べ物にならないプレッシャーを感じる。
簡単に追い払えるとは思えないが、逃げられるとも思えない。
考える間もなく、再度トンボの周囲で空気が唸る。
ジムノはとっさにルエリシアを突き飛ばし、彼女とは反対側に跳んだ。
「きゃっ……!」
やはり足元が砕ける。
おそらく空気の塊を刃にして飛ばしてきている、といったところか。
「くそ、厄介だな……」
見えない攻撃。しかもかなり速く、少なくともルエリシアには対応できないと考えていいだろう。
それならまずは彼女だけでも安全なところに――と行動に移す前に、次の異変が起こる。
キィ、と高い音が一瞬だけ響いた。――というより、おそらく人の耳で捉えられない高さの音なのだろう。このトンボの鳴き声か、と警戒し、それから――
「――」
――それから?
「っ、う……」
思考をかき回されるような感覚に、五感が乱されるような気持ち悪さに、気が付くと膝を付いていた。
「ジムノくんっ!?」
平衡感覚がおかしい。
今、何をしているのだったか思い出せない。
吐き気のような、眩暈のような。
ここはどこだ?
ああ、そうだ、化け物から逃げないと。
「大丈夫!? 一体何が……」
……逃げる? 何故?
誰かの声が響いて。
誰だ。
駄目だ。膝ですら立っていられない。
ぐるりと視界が回る。
どうしてこんなことになっているのだったか。
逃げる必要なんてない。消えればいい。殺せ。殺してくれ。
「いや……っ」
ごと、と自分の頭が音を立てるのを知覚した。
どこかに打ち付けたらしい痛みだけは妙にはっきりと響いて、少しだけ思考がクリアになる。
そうだ、化け物だ。
化け物に襲われているんだ。
感覚が乱されて、力が上手く入れられなくて、そんな彼を庇うような体勢で、ルエリシアが涙目でこちらを見下ろしてきていて――
「っ……!」
そうだ。彼女だけでも先に逃がさないと、と考えていたのだった。
彼女さえ無事なら自分の傷は多少はなんとかなるのだから、自分が引き付けて彼女を逃がす方が二人とも生き残れる可能性が高くなるはずなのだ、と考えていたのだった。
「……逃げ、ろ」
なんとか声を絞り出すが、ルエリシアはぶんぶんと首を左右に振る。
「いや!」
彼女はパニックになっているのか、ジムノの手首を握りしめて悲鳴のような叫びを上げた。
また、低く空気が震える。
ルエリシアはそれに気付いて、恐怖の色が滲む表情で化け物の方を振り向く。だが逃げる素振りを見せない――どころか、やはり彼の頭を庇うように抱き締めてくる。
だめだ。
やめろ。
「馬鹿、早く、逃げろ、って……!」
彼の叫びに重なり、アスファルトの砕ける音が間近に響く。
放たれた空気の刃は、彼女の背後に着弾した。
「――っ!」
ルエリシアが声にならない叫びを上げる。赤い飛沫が空中を舞うのが、やけにゆっくりと見えた。
痛みはない。つまり。
「ルエリシア!」
血の気の引く感覚。無理矢理身体を起こす。頭がまだぐらぐらするがどうでもいい。
運良く直撃は避けられたものの、攻撃が背を掠めたらしい。彼女の身体は血まみれで、痛みに耐えるように声を押し殺している。べっとりと血が染みた服に隠れて傷の状態までは分からないが、致命傷ではなくとも動けはしない、といったところか。
「……」
これで逃げるという選択肢はなくなった。彼女を守りつつ、倒すか追い払うかしかない。
「……この……化け物め。僕が、相手だ」
もちろん言葉が通じるとは思っていないが、なんとか彼女から注意を逸らすために声を上げ、隙を見せないようにしつつ手近なコンクリート片を手に取り、ゆっくりと立ち上がる。
自分だけなら逃げられるかもしれない。だが、昨晩心に決めたばかりだった。自分を否定しないでいてくれる人くらいは守りたい、と。
ここで彼女を見捨てるようなことをすれば、絶対に後悔する。
「ジムノくん……だめ……逃げて……」
「……いいから黙って傷を治していろ。逃げろと言っても逃げなかったのは君だ」
彼はルエリシアの掠れた声にそれだけ答えると、二人をあざ笑うように飛び回る化け物と対峙した。
化け物の視線が自分に向いていることを意識しながら、じりじりと彼女から離れてゆく。
次に来るのは妙な鳴き声か、それとも空気の刃か。
その動きに注意を払い、耳を澄ます。
――相手はただ強いだけではない。彼にとってはあまりに不利なのだ。
体当たりしてくる兎くらいならともかく、空を飛び回り一方的に飛び道具を放ってくる相手はどうしようもないと言っていい。
苦し紛れにコンクリート片を手にしてみたものの、高さも距離もある素早い相手に投げ付けたところで当たるとは思えない。
ひとまずは慎重にルエリシアから引き離しつつ攻撃を避け続けるしかないのだが、それで状況が好転するとも思えない。いや、時間さえ稼げれば治療を終えた彼女の加勢を期待できるかもしれないか。
そこまで考えて、ジムノは内心苦笑する。
ルエリシアに庇われて、それでもまた自分では何もできずに彼女の力に頼るしかなくて。
これではあまりに――
「……いや」
そんなことを考えている場合ではない。やれる限りのことをやるしかない。
トンボはまたも空気を震わせ、見えない刃が飛来する。彼は勘だけでなんとかそれを避けるが、そこにトンボが急降下してくる。
刃を避けて体勢の整わないところを狙ってきたらしく、思った以上に知能まで高いらしい。
だが。
たとえ体勢を崩そうが、手の届く範囲まで下りてきてくれるというのなら絶好のチャンスだ。
立て直すのを敢えて諦め、代わりにコンクリート片を握り直した左手に集中する。
異様な速さで化け物が眼前に迫り、一メートル先に届くそのタイミングで思い切り殴りつけた。虫を潰す気持ち悪い感覚が手先から背中までを駆け抜ける。
そしてそのままバランスを崩し無様に尻餅をつくが、すぐさま立ち上がって構え直す。
ギィ、と耳障りな悲鳴を上げたトンボは大きく舞い上がり、警戒するように再び彼を見下ろした。やや飛び方がぎこちなくなっているものの、思ったほどのダメージは与えられていないようだ。
だがここで逃げ出してくれなければ困る。警戒しているのならばまた同じように突っ込んできてくれるとは考え難い。
数秒ほどそのまま対峙し――
唐突に、トンボが再び悲鳴を上げた。
バランスを崩し落下しそうになるが踏みとどまり、そして逃げるようにふらふらとどこかへと飛び去って行く。
代わりに羽の一部だけがぼろりと崩れて舞い落ちていった。
「――」
ジムノは身構えたまましばらくじっとしていたが、それ以上何かが起こる気配はない。
詰まっていた息を大きく吐き出し、膝をついた。肩で息をする。
今更のように心臓がやたらと速く脈打っていることにも気付いた。相当緊張していたらしい。
目の前に、トンボの羽の一部が落ちている。
それは妙にきらきらと光を反射していて、彼はトンボが逃げて行った理由を理解した。
「……凍っている?」
そんな芸当ができる人間には一人しか心当たりがないのだが、ルエリシアの方をちらりと見ると、彼女はうつ伏せに転がったままだった。
ジムノはふらふらと、少し震える足で彼女に歩み寄る。
「……ルエリシア」
声を掛けると、彼女はゆっくり白い顔を上げ、やや青くなった唇を小さく開いた。
「っ……。……あれ……? 終わった、の?」
やはり彼女の仕業ではないようだった。この状態であんなことができるとも思えない。
となれば、ルエリシアと同じような力を持つ何者が助けてくれたというのか。
辺りを見回してみるが、トンボの姿は既になく、他の化け物や人の影もない。
「……ああ。なんとか、逃げていってくれたようだ」
彼はそれだけ答えた。
「治療、終わった……かも」
彼女はそう呟いて、身体をゆっくり起こした。
大量の血に染まった服は痛ましいが、顔色は少しだけ良くなっている。
調子を確かめるように身体を軽く動かしてから頷いた。
「よし、大丈夫。ごめんね、待たせちゃって」
「いや。僕の方こそ……。……足を引っ張ってしまって、悪かった」
とりあえず一度帰ろう、と、まとめ直した荷物を持って立ち上がった。
「そんなことないよ」
彼女が持とうとした荷物も奪って歩き出す。
ルエリシアは立ち上がり、小動物のような足取りで隣を歩き始めた。
「ジムノくんがいてくれなかったら、きっと何もできないまま死んじゃってたもん」
彼はそれを黙って聞く。
確かに彼女の言うとおりかもしれないが、それとこれとは別だ。彼女が自分を庇って大きな怪我をした、という事実が胸に突き刺さって抜けない。痛い。
「だから、大丈夫。ありがとう」
ルエリシアはにっこりと笑う。痛くて苦しくて、でもそれを何と言えばいいのか分からない。
「……ああ」
結局ぼんやりと頷くだけの自分が嫌いだ。
なんとか帰り着いた拠点のコンビニは、人や化け物が侵入したような形跡もなく、出掛けた時と変わらない様子だった。
「……よかった……」
中に入るなりそう小さく呟いて、ルエリシアはその場にへたり込む。
「っ、おい、大丈夫か!?」
ジムノが荷物を置いてきっちり扉を閉めてから彼女の隣に膝をつくと、彼女は彼の顔を見上げてきて、その目にじわりと涙を滲ませた。その様子に思わず慌てる彼に構わずすがり付き、声を殺して泣き始める。
「帰ってこられて……よかったよ……」
嗚咽の混じる声に、胸がぎゅっと苦しくなる。
「ああ……そうだな」
答えると、彼女はさらにぎゅうぎゅうと強くしがみついてきた。
彼はそれにどう応えればいいのか分からず、血がこびりつき乱れたままの髪をぎこちなくもそっと撫でてみる。
「怖かった……」
「そうだな」
幸運が重なって助かったが、どこかで一歩間違っていれば今頃どちらかが、もしくは二人とも、死んでいたかもしれない。
「……ごめんね。冷静な判断ができてるだけでもいいって言ってくれたのに……ジムノくんが消えちゃうかもって思うと、ダメだった。こんなんじゃ……わたし、役になんて立てないよ……」
「……いいんだ」
ひどく落ち込んだような様子のルエリシアに、ジムノはかぶりを振った。
自分が余計なことを言い過ぎたのではないかと不安になる。
今は、二人とも無事で戻って来れただけで充分だ。
「その……。……消えないでほしいと言ってくれて、嬉しかった」
「えっ?」
予想外の言葉だったのか、彼女は驚いたような顔を上げる。
「僕は……消えても構わないと言ったが、それどころか、消えたいと思っていたんだ。あの時にじゃなく……そう、ずっと、昔から」
まっすぐな眼差しに耐えられず、少し視線を外した。
「……そんな」
「何しろ、誰からも必要とされず、嫌われてばかりだったんだ。自分が存在する意味なんてない……いや、それどころか害にしかなっていないんだろうと思っていた」
だから、と薄く笑う。
「消えないでほしいと思ってくれるだけで、必要としてくれるだけで……僕には充分だ。役に立つからとか、そういうことではなくて……その」
それ以上はなんと言えばいいかわからなかった。
気に病まないでほしい。泣かないでほしい。――いや、きっと根本的にはそういうことではなくて。
反応が怖い、と思う彼の手を取り、ルエリシアもまた何かを怖れるようにこわごわと口を開く。
「……ホントに? わたし、これからも迷惑をかけることはたくさんあると思う。それでも……一緒にいて、いいの?」
――一緒にいたい。
ああ、そうだ。それだけのことだ。
「当然だ」
彼は即答する。
それにルエリシアはまた涙を零し、ぎゅっと抱き付いてきた。
「お、おい。何故君が泣くんだ」
慌てるジムノに、彼女は肩を震わせながら、
「だって! だって……っ」
と声を上げかけ、そのまま嗚咽で何も言えなくなった。
乾いた血のこびりついたぼろぼろの背中が揺れる。
替えの服を早く調達してこなければ、とどこか冷静に考えながら、ジムノはその背中を黙って見下ろしていた。
髪に付いた血はドライシャンプーなんかで上手く取れるものなのだろうか。長期間になると風呂がないのは随分困りそうだ。
ぼんやりと考えるだけでも後から後から問題が出てきて、ただ、今はそれよりも。
随分疲れた。
きっと彼女もそうなのだ。
今日だけじゃない。何があったのかは知らないが、ずっと昔からそうなのだ。
自分をすり減らして他人を助けようとして、ジムノが何も言わないうちから役に立つことに拘って。
彼女もきっと疲れていたのだ。
「……ルエリシア?」
震えていた肩はいつの間にかゆっくりと微かに上下しており、彼の呼び掛けには応えない。
どうやら眠ってしまったようで、彼がその顔を覗き込むと、赤く泣き腫らした瞼を閉じ、緩やかな寝息を立てていた。
抱きついたまま眠れるほど信頼してくれているのか、と思うと頬が緩みそうになる。
頬に残った涙を指先で拭ってやる。伝わってくる体温と柔らかさに、また、苦しくなった。
必要としてくれることが嬉しくて。
一緒にいてほしくて。
彼女が死んでしまうかもしれないと思うと怖くなって。
幸せそうな姿を見ると幸せな気分になれて。
彼女の力になりたいと思って。
――そんな感情が、全部、苦しく感じて。
「……もしかして」
彼は一つの可能性に思い当ってしまった。
もしかして、僕はルエリシアに恋をしてしまったのではないか――と。
「……ん、う……」
ルエリシアは小さく呻いて、うっすらと目を開いた。
「……起きたか?」
「ん……」
ジムノが声を掛けると、彼女は肯定とも寝ぼけているだけともつかない声を漏らして、さらにしばらくしてから、ゆっくりと身体を起こした。
「あれ……? わたし、いつ眠ったんだっけ……」
ぼんやりとした声を上げてから、寒そうに身体を縮める。
ジムノはそれには答えず立ち上がった。
「着替えを調達してくる」
そう言うと彼女ははっと目が覚めたように顔を上げる。
「えっ……ま、待って、一人で? 今から?」
「一番近そうな、斜向かいの店を見てくるだけだ。すぐに戻る。何かあったら駆け付けるし、僕だって無理はしない」
「でも……」
「ずっとその格好のままというわけにもいかないだろう? 僕もいい加減着替えたい。暗くなる前になんとかしたいが、君は今万全の状態じゃない。違うか?」
う、と彼女は反論を止めた。
たとえ傷は塞がっていても、流れ出た血が元に戻るわけでもないだろう。単純に体力も消耗しているはずだし、サイキックを使ったことも考えると、早く食事でも摂って休んでいなければいけないはずだ。
だが彼女は、心配するような、申し訳なさそうな顔を上げたまま、何か言いたげにきゅっと唇を噛む。
「そんな顔をするな。君は身体を張って庇ってくれたんだ。これくらいはさせてくれ」
「……うん……。……じゃあ、本当に、気を付けてね?」
「ああ」
短く答えると、まるで逃げるように外へと滑り出る。
早く一人で頭を冷やしたかった。
一度意識してしまったせいか、冷静さを失っているように感じたのだ。
眠ってしまった彼女を店の奥へと運ぶために抱き上げたとき、乾いた血と埃にまみれた小さな身体が、何故か良い匂いのような気がしたり。
理由もなくその寝顔に触れてしまったり、少し傷んだ髪を撫でてしまったり。
「……何をやってるんだ、僕は……」
そんなことで心を乱していられるような状況ではないはずなのに。
彼は一度深呼吸する。緑の匂いは心地良くも気味が悪い。
昨日の地獄のような光景が嘘のように、外には穏やかな景色が静かに広がっている。人間が消え、化け物も今朝のトンボ以外には現れず、樹海と同化した廃墟のようなビル群が立ち並ぶ。
彼女に伝えた通りの斜向かいの建物は地下から生え出した大木に一部を崩され、一階の衣料品店も入口のガラスが割れているが、侵入する分には差し支えなさそうだ。
ジムノは慎重に中の様子を伺う。どうやら中には化け物も人間もいないようで、荒らされたような形跡もなかった。
入口近くの商品はガラスの破片を被っているかもしれないので避けておき、奥の方から物色することにする。
自分用に、適当なシャツの半袖と長袖を少しずつ。サイズの合っていそうなパンツ。インナー類は見当たらないがコンビニにあったはずだ。
「しかし……」
彼は溜息を吐いた。
「……一時の気の迷いというか、典型的な吊り橋効果というか……」
自分のあまりの単純さに呆れる。
ただ嫌われていないというだけじゃないか、と自分に言い聞かせようとしてみる。
そんなこと、大多数の人間にとってはあまりにも普通の、当然のことで――
だが、彼にとってはそうではないのだ。
否定しないでいてくれて、消えないで欲しいと思ってくれて。
助けてくれて、心配してくれて。
それだけのことでも、苦しくなるほどに嬉しいのだ。
そして、そんな風に接してくれる彼女の力になりたいと、自然に思えたのだ。
今まで他人を利害でしか量らなかった自分が。
助けたい。守りたい。笑っていてほしい。そう、思えたのだ。
――頭を冷やしてみたところで、ルエリシアに対して好意を持っているのは明らかだった。
それが本当に恋愛感情に類するものかどうかは証明しようもないしその証明に意味があるとも思えないのでさて置いて、冷静に考えれば考えるほど、少なくとも好意であることには間違いないように思える。
これが仮に気の迷いとしても、しかしそんな風に思ったのは事実であって……その感情を疑う必要はあるのだろうか?
ない、と思う。
それなら、何か問題があるか?
冷静さを保てなくなるのは困る。服を取ってくるなんて言い訳をして一人で出てくる時点で手遅れのような気もする。
けれど、彼女が必要としてくれなければ――それに応えたいという思いがなければ、自分は一体何に執着して生きられるのだろう。昨日だって、今日だって、仕方がないと言って諦めていたはずだ。それなら冷静でいられるかどうかなんてどうでもいい。やれるだけはやった、と思えればそれだけでいいのだから。
ルエリシアがいてくれるから、生き延びたいと思えたのだ。この感情に問題があるとかないとか、考えること自体がナンセンスではないか。
「誰かと一緒にいたくて生きたい、か」
言葉にして、笑ってしまった。昨日までの自分からは到底出てこないであろう言葉だ。
少し気を抜くと死んでしまいそうな世界になって初めて、こんな風に思えるなんて。
「何も問題ないな」
ルエリシアと一緒にいたい。隣にいてほしい。きらきらとした表情を見ていたい。そのために生きる。
「そのために……まずは服を持ち帰らないとな」
彼は女物の服が所狭しと掛けられた棚の前に立つ。
そういえば、誰かのために服を選んだことがない、と気が付いた。
兄や姉が彼の服を選んでくることはあっても、逆はなかった。
自分より二回りは小柄な少女の服をどうすべきか、ジムノはじっと棚を睨んで真剣に考え込む。
彼女のことを考えながら選ぶのは妙に幸せで、そして経験したことのない難問だった。
ガラスの扉を手で引き開けると、少しは体力の戻ったらしいルエリシアが飛びついてきた。
「っ……!? お、おい……?」
「遅かった!」
慌てるジムノに、彼女は少し怒ったようにそう声を上げた。
「すぐ戻るって言ったのに」
心配させてしまった、という申し訳なさと、心配してくれた、という心地良さが入り混じる。
「……すまない」
彼は素直に謝り、後ろ手に扉を閉めた。
彼女ははっとして小さくかぶりを振ると、
「あっ……ううん、ごめんね。わたしのために一人で行ってくれたのに。……何も、変わったことはなかった?」
と、不安そうな顔で見上げてきた。
「ああ。ただ、その……。どんな服を選べばいいか分からず……」
正直な言い訳をしつつ、彼はルエリシアのためにいくつか拝借してきた服を手渡す。
「最低限……サイズが合えばいいんだが」
ルエリシアは受け取った服をひとつ広げてまじまじと見つめ、
「大丈夫だと思う。ありがとう」
そう言ってにっこりと笑った。
ジムノはその表情にほっとして、肩の力を抜く。それにルエリシアは首を傾げた。
「……あれ? 少し顔が赤いかも……そろそろ休んだ方がいいんじゃない?」
「い、いや。これは体調が悪いとかじゃなく……。僕はまだ大丈夫だ。君の方こそ……」
「ううん、わたしはさっきしばらく眠ったし、これから食事も取っておきたいから、いいの。ジムノくんは昨日ほとんど寝られてないんだし、眠れるうちに……ね?」
そこまで言われて固辞するのもおかしい気がする。彼は頷いた。
「……わかった、ありがとう。じゃあ、着替えたらしばらく休ませてもらう」
「しばらく、じゃなくて。一度ちゃんと休んで」
きっぱりと言って少し頬を膨らませるルエリシア。これはこれで可愛い、と考えてしまってから、わかったわかった、と頷いた。
――いつ何が起こって死んでしまうかも分からないこんな状況になって初めて、他人を好きになってしまった。生きてこの時間を過ごしていたいと思ってしまった。世界が初めて色彩鮮やかに見えたような、支えのないぐらついた足場に立っているような、経験したことのない感覚。
どうか、明日も明後日も、一日でも長く続いて欲しいと、彼は祈る。